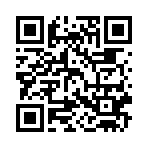2023年11月30日
2024年度「宅建士合格講座」開講のご案内
来年も、SBS学苑にて「宅建士合格講座」を開講致します。
例年、数多くの合格者を輩出している、歴史と伝統のある講座です。
さあ、あなたも、この講座に通って「合格」の栄冠を手にしましょう!
※ 講師から学苑への紹介の場合、受講生に「特典」がありますので、
お知り合いにこの講座をご紹介下さる場合は、
まずは久保までご連絡下さい(054-247-9495)。
講座検索|やりたいこと、きっと見つかる! 静岡県のカルチャーセンター (sbsgakuen.com)
[開講日]
パルシェ校 (☎054-253-1221):3月5日(火) 18:30~20:30
沼 津 校 (☎055-963-5252):3月7日(木) 18:30~20:30
浜 松 校 (☎053-455-3359):3月8日(金) 18:30~20:30
[無料ガイダンス]
①12/19(火) ②1/23(火) ③2/13(火) 各校にて
※詳しくは、学苑各事務局までお問い合わせ下さい。

2023年11月29日
合格体験記 2 (下)
<10月:いちばん大切な2週間:試験週の金曜日は会社を休みました。>
・SBS学苑模擬試験 結果:29/50点 本試験の1週間前に、
この模試を受験したことが合格につながったと思う。
→心境:業法が11点しか取れないってどういうこと。
試験1週間前にして最低点。LECの問題傾向に慣れていた私は、
傾向が変わると思うように点数が取れなかったが、逆に本番でなくてよかった、
1週間後に敗者復活でもう一度試験が受けられる。といい方に考え勉強に集中できました。
・試験前の金曜日と土曜日は1日中、Youtubueを見まくってました。
特に宅建業法の35条、37条に関する動画は何度も見ました。(1.5倍速)
<点数の積み上げ方>
これは10/9の模試を受けた後に自分なりに考えた戦略ですが、
50問を宅建業法:20問とその他:30問に分けて考え、
①その他の30問で20点をどんな形でもいいので死守する。
②宅建業法は限りなく満点を目指す。
③民法を制する者は、宅建を制す。
(そんなにできなくてもいいけど、大崩れしない力をつける。)
<試験本番の心得>
①試験会場には早く到着しましょう。
→机がガタガタする場合がある。さっさと申し出て交換してもらいましょう。
(遠慮は禁物です。)
②マークミスに細心の注意を払う。私のように合格基準点で合格の場合、
マークミスが致命的となります。
③試験終了後、すぐに自己採点するためにも、
問題用紙に自分がどのように解答したのか、はっきりわかるように明示しましょう。
<私からのメッセージ>
・基本の”き”を大切にする。→みんなが出来る問題を落とさない。
・努力が必ず報われるとは限らない。でも、報われるまで努力する。
宅建試験は難関試験だと思います。100人受けて17人しか合格出来ないし、
でも、あきらめなければ必ず合格出来ると思います。
私でも合格できたのですから、あきらめるか?合格するかです。
自分自身が主導権を握っています。がんばってください。

2023年11月28日
合格体験記 2 (中)
M.K さん(「短期集中講座」 50歳代 男性)
(続き)
<7月~8月>
*ポイント
・宅建試験の申し込みが始まったら、すぐに試験の申し込みをしましょう!
→受験番号の早い人は合格に対する意識も高く、本番の受験会場の雰囲気が乱れません。
・7月のLECの0円模試は必ず受験すべき 結果:30/50点
ここで宅建業法でどれくらい得点できているかを確認する。
→心境:あまり得点できず、今年もダメかな的な心境。
ただ、結果に一喜一憂することなく、復習に専念した。
7月からは「宅建士 合格のトリセツ 分野別過去問題集」 LEC 友次正浩を解き始める。
*この時、問題のページには絶対に書き込みをしないようにした。
(理由:問題に書き込みをするとわかったつもりになってしまうため。)
<ターニングポイント>
7月19日より「SBS学苑 宅建短期集中講座」を受講。
目的:
・週の真ん中、水曜日に学習のペースメーカーが欲しかったため。
・社会人にありがちな土日集中型の勉強方法は、
結局、1週間まるまる空いてしまい知識の定着がよくないと考えたため。
・この時期にもう一度、民法の復習をしたかったため。
*講義受講時の心得
私は、勉強方法が自己流だから合格できないんだ。と考え、
久保先生のいうことを素直に聴くことを心掛けました。
実際は、仕事帰りでもあったため、寝落ちしてしまうこともありました。
講義中は、久保先生の話している内容を心の中で真似してつぶやくようにしていました。
→よく理解できない用語が出てくるたびに調べ、”索引”にマーカーをした。
2回目以降は問題をランダムに解くようにした。
→同じ単元を連続して解くとわかったつもりになってしまう。
・スマホのアプリを活用し、一問一答を繰り返す。
・「宅建みやざき塾のさくっと3分トレ」 中央経済社 宮嵜晋矢を繰り返した。
すき間時間に1単元3分で学習可能。出かけるときはいつも持ち歩いていた。
→この本は図表も非常にコンパクトにまとまっているため、
試験の前日に出そうな所にポストイットを貼って、試験会場で確認をしながらはがしていきました。
<9月>
・LECの模擬試験 結果:32/50点
→心境:あまり進歩してないな。(笑)
→間違えた問題、弱点は、テキスト、一問一答に戻ってやり直した。
・反省点:動画解説がすごくよいため、時間を作ってもっと復習すべきだった。
・同時並行で、分野別過去問題集を繰り返した。(必ずランダムに解く)
(続く)

2023年11月27日
合格体験記 2 (上)
合格体験記
M.K さん(「短期集中講座」 50歳代 男性)
ようやく宅建に合格することができました。(ぎりぎりの36点ですが)
両手まではいきませんが、私はこれまでに5回以上宅建試験を受験しています。(笑)
受験生の方が必要としている情報は、実際にどの時期に、どのような行動をしたのか?
ということだと思うので時系列で事細かく書かせていただきます。
私は2月から宅建の勉強をスタートしました。
*宅建の勉強をスタートする前に読んだ本。
「大量に覚えて絶対に忘れない紙一枚勉強法」 棚田健太郎
*宅建試験は忘却との戦いです。
・毎日のノルマ
①X(twitter)有山あかね @4riy4m4
宅建あと〇〇日を100均で購入したカードに書き写して理解することを心掛けた。
→宅建試験まであと何日かわかるのでモチベーションがあがる。
→この時期にカードをきちんと作成しておくと、
試験会場で直前のチェックに非常に役に立つ。(実際に本番で助けられました。)
②Youtubue:棚田行政書士の不動産大学を見る。毎日18:00~
常に一定のペースで勉強を続けることを心掛けた。
「宅建士合格のトリセツ 基本テキスト」 LEC 友次正浩
*民法は5月のGWまでに1回転することを心掛けた。
「いちから身につく 宅建合格のトリセツ 一問一答 800問」 LEC 友次正浩
→いちばんお世話になった問題集。
*何度、本試験を受験しても30点くらいしか取れないのは、
選択肢をきちんと判別できていないのが原因と分析。
とにかく一問一答をきちんとやることが合格の土台と考え、
きちんと計画を立てて実行した。
朝起きて、今日は何しよう。という勉強法はいけないと思います。
計画をたて、それを粛々とこなすことが大切。
→3回転を目標とした。(不思議なもので、3回やって3回とも間違える問題が
けっこうあった。このような問題は、試験本番でも必ず間違えるので、
なぜ間違えたのかきちんと対処する必要がある。)
6月まではとにかく一問一答を繰り返し、理解が浅い単元は基本テキストに戻った。
近年増加している個数問題に対応するためにも一問一答を繰り返すことが大切です。
(続く)

2023年11月23日
合格体験記 1
『合格体験記』が届いておりますので、
順次掲載させていただきます。
来年度に受験を予定されている皆さんは、
「合格者」のリアルな思いをぜひ参考にして、
同じく「合格」の栄冠を手にして下さい。
======================
合格体験記
T.K さん(パルシェ校 50歳代 男性)
昨日合格発表があり、晴れて合格することができました。
昨年初めての宅建試験で不合格となり、この試験の厳しさを肌で感じ
リベンジを果たすべく2回目の試験に挑戦しました。
「昨年の勉強は本当に真剣に取り組んでいたのか?」、
「何が足りなかったのか?」、「自分の苦手分野はどこなのか?」、
「知識は定着しているのか?」、
等々自問自答し、今年の目標を「理解」に定め取り組んできました。
思えば昨年は、一つ一つの課題を上辺だけ学習(?)し、
解ったつもりになり、過去問を繰り返すことだけに満足していたように思います。
そんな時、久保先生の「急がば回れ」の言葉に、もう一度テキストに帰り、
何故この結論に行きつくのかを理由を含め考えながら読込むことで、
理解から知識へと変換することができたと思います。
宅建試験は暗記項目が多いのは事実と感じますが、その暗記項目も
全て理由があると考えられますので、昨年の「勉強のための勉強」から
「理解のための勉強」に切り替えられたのが合格へ近づいた
大きな一歩だったような気がします。
もう一つ実践したことがあります。
それは、どんなに忙しいときでも、
必ず毎日一回は(5分、10分でもいいので)、
宅建試験関係に触れておくことでした。
「テキストを読む」「一問一答を解く」等、
何でもいいので休まずに続ける事でした。
それにより学んだ事を忘れてしまわないようキープできるかと思います。
今年合格に導いて下さった、宅建講座の久保先生には感謝の言葉しか
ございません。
本当にお世話になりました。有難うございました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【講師より】
毎回熱心に受講され、多くの深みのある質問もされた方です。
受験生にとって大切なのは、
つどつど自問自答し、反省し、軌道修正していく、
謙虚で、前向きな心持ちです。
それを体現され、見事に「合格」を勝ち得たKさんに
心からの拍手を送りたいと思います。
本当におめでとうございました。

2023年11月22日
「合格体験記」ご執筆のお願い
下記要領に基づき、
後に続く受験生のためにご教示下さい。
[執筆要領]
1. 分量・形式/特に制限はございません(分量の調整・段落分け・校正などは
こちらで行いますので、気楽にお書き下さい)。
2. 内容(例)/自分が行った学習方法(何月の時点で何をやったか)
本試験までに考えたこと・感じたこと
3. 送付方法/メール(tko@press-a.com) またはFAX (054-204-5537)
※年末のお忙しい時期に恐れ入りますが、12月中にはお送り下さい。
どうぞよろしくご協力のほどお願い申し上げます。

2023年11月22日
「合格発表」について
不動産適正取引推進機構が発表した、実施結果の概要によれば、
今年の合格基準点は36点、合格率は17.2%でした。
有難いことに、
合格された方は、ご自分の記念にもなりますから、
そして、今年は残念ながら合格されなかった方は、
来年は必ず「合格」できるように、今から少しずつ準備を始めましょう。
宅建は、『受かるか、受からないか』ではなく、
『受かるか、あきらめるか』の試験です。
あきらめたら、そこで終わりです。
そして、このくらいの難易度の試験になりますと、
さあ、私と一緒に、必ずや栄冠を手にしましょう!