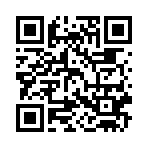2020年02月20日
事前に読んでおきたい「法律の入門書」
その「合格講座」第1回目の「講座の進め方」でもお話ししますが、
皆さんとは最初に、民法を学習するということもあり、
できれば、事前に読んでおいていただきたい本があります。
それは、伊藤 真(著) 「伊藤 真の民法入門(第6版)」(日本評論社
1700円:税別)です。
伊藤 真(まこと)氏は、言わずと知れたLEC創成期の司法試験部門を
作り上げた方で、法律系国家資格指導の第一人者です。
現在は、護憲派弁護士としても活躍されています。
民法は、我々の日常生活に密接な関係のある、非常に重要な法律です。
法律上の「人」とは何かから始まり、契約(売買や賃貸借)・債務不履行・連帯保証・
抵当権・時効・相続等、ビジネスでも有用な知識を学習します。
ただ、我々が講座で使うテキストが、
(当たり前ですが)受験対策として書かれたテキストのため、
ともすると、とっつきにくく、本来ならおもしろく、ためになるはずの民法の良さが
伝わりにくい恐れがあります。
そこで、この「民法入門」を事前に読んでおけば、比較的スムーズに、
民法のおもしろさを理解していただけると思うのです。
「民法入門」は口語体で書かれているため、
200ページほどの分量ですが、一気に読めてしまいますよ。
さあ、皆さん、今すぐ大きな書店あるいはアマゾンにて、
この本を手に入れて下さい!
そして、法律学習の”核”である民法を、好きになりましょう!

2020年02月19日
「再受講」を検討されている方へ
いよいよ本年度の開講が近づいて参りました。
さて、今現在「再受講をしようか否か」で迷っていらっしゃる方も
おられると思います。
受講には、お金と時間がかかりますから、迷うのも当然です。
そのような方に、私はこうお伝えしたいです。
「今年 合格するために、もう一度だけ私と一緒に、がんばりましょう!」
10月の本試験までは、足かけ8か月の長丁場です。
そこで、まず考えるべきなのは、「ペースメーカー」です。
「合格したい!」という気持ちを、本試験まで維持するために、
週1回の講義を聴きに来て下さい。
昨年も、再受講の方が何名か「合格」されています。
宅建は、受かればいいのです。
「合格」したら、それまでに何度受験したかなどは関係ありません。
ご自分の人生を劇的に変えるためにも、
もう一度だけ、私と一緒に高みを目指しましょう!
ご受講をお待ちしております。
※ ご受講が決まりましたら、早目に事務局へ連絡してあげて下さい。
http://www.sbsgakuen.com/

2020年02月16日
早期 お申し込みのお願い
いよいよ3月第1週から、3校で順次<開講>致します。
さて、現時点で、すでに受講をお決めになっている方にお願いがあります。
受講する」旨のご連絡を、早目に (できれば本日中にでも)、
SBS学苑 事務局にしてあげて下さい。
事務局では、皆さんがお使いになる、テキストを出版社に発注
しなければなりませんし、私も、第1回目の講座で使用するプリント類を
必要部数だけ用意しておかなければなりません。
ですので、早目にご連絡いただけると、たいへん助かります。
■沼津校 : 055-963-5252
■パルシェ校 : 054-253-1221
■遠鉄校 : 053-455-2230
どうぞよろしくご協力のほど、お願い申し上げます。

2020年02月16日
合格体験記 11
SBS学苑 イーラde沼津校 S.A さん(沼津市 40歳代 女性)
初めての「宅建試験」でしたが、1回の挑戦で合格することができました。
久保先生、ありがとうございました。
■「宅建試験」を目指すきっかけ
私は、「宅建試験」とはあまり関係のない、福祉関係のケアマネージャーの
仕事をしていますが、自分自身の知識を増やしたいことと、
以前より不動産関係に興味があったため、「宅建」を受験しようと決め、
独学でやろうかと書店で「宅建」の本を購入し、勉強をし始めましたが、
まったく知識のない状態では難しいと感じ、SBS学苑のガイダンスに行き、
受講を決めました。
■学習方法
私の学習方法としては、まず毎週の講義を休まず受講し、
「要点整理テキスト」と過去問を中心に、何度も復習するようにしました。
自分の仕事が忙しかったため、書面を見れないときは、YouTube の
動画なども聴きながら勉強をしました。
■SBS学苑の講座を受講して良かった点
やはり、独学ではわかりにくい点を久保先生が強調して説明して下さったことと、
『今の時期には、過去問をここまでやらないといけない』など、
学習上のアドバイスをもらえることで、合格へのモチベーションを保ち続けられた
ことだと思います。
初めての受験で「合格」できるように導いていただいた久保先生に感謝しています。
ありがとうございました。

2020年02月10日
「合格体験記」からの考察
読み進めていくと、その学習方法等にいくつかの共通点があることがわかりましたので、
私なりにまとめさせていただきます。
◆学習方法
□学習の導入部として、「伊藤 真の民法入門」や「マンガ宅建」などが有効だった。
□<四肢択一式>の問題に慣れたら、知識の精度を上げるための
<一問一答式>による鍛錬が有効だった。
□講義を録音したものを、スキマ時間を活用して、繰り返し聴いた。
◆学習時間の確保
□仕事や子育てで多忙ではあったが、意識的に学習時間を確保するように努めた。
◆印象に残った講師の言葉
□『宅建を取れば、一生の間、他人から尊敬される』という言葉に励まされた。
□『最後まであきらめるな』という言葉に、あと押しされた。
□「他流試合」(=LECや日建学院など、他スクールの模擬試験を受けること)を
推奨されていたので、積極的に受験した。
◆その他
□講師からの指導(ブログを読む、プリントを貼るなど)は、愚直に、
即日対応するように心がけた。
これから受験に臨む皆さんは、こうした合格者の体験を、ぜひ参考にして下さい!
次に「合格体験記」を書くのは、あなたです!
http://www.sbsgakuen.com/Detail?gakuno=2&kikanno=198515

2020年02月09日
合格体験記 10
SBS学苑 パルシェ校 N.H さん(藤枝市 60歳代 男性)
■受験のきっかけ
建設業関係の仕事のため、「宅建」資格を持っていても良いものと考えました。
日常的に、お客様と不動産関係の話をするので、その際に、
「もう少し、知識が必要だな」と感じていました。
■「合格」までの道のり
今回は、4度目の挑戦でした。
1、2年目は「合格講座」に、3年目は「実力養成講座」に通い、
4年目は「答案練習・直前予想模擬試験」のみ通いました。
4年間も挑戦したおかげで「権利関係(特に民法)」「宅建業法」「法令上の制限」も、
暗記ではなく、だいぶ理解できるようになりました。
■4年目の学習方法
過去問は、住宅新報社の「パーフェクト宅建」シリーズの<一問一答式>問題集を
使用しました。
今までは、四肢択一方式の過去問をたくさんやっていましたが、
やはり<一問一答式>の過去問をやりますと、自分の弱いところがよくわかり、
間違えた問題は何回もやりました。
また、問題文の”ひっかけ”に、よくひっかかるので、問題文を読むときは注意して、
「正しい」のか、「誤り」なのか、確認しながら、問題文を読み進めました。
過去4年間分のSBS学苑の「答案練習」と「模擬試験」の問題もありましたので、
それも、間違ったところを徹底的にやり直しました。
■4年間を振り返って
私は「合格」に4年間かかりましたが、やはり自分で勉強時間を作って
やるしかないと思います。仕事が忙しかったり、甘い誘惑があったり、
家庭の事情でなかなか勉強時間が取れなくて、「今日は、まあいいか」
という日は何回もありましたが、でもやはり、「今年は合格したい!」という思いで、
空き時間を作って、机に向かって過去問を解きました。
自分でも、「4年目の合格も、ちょっとたいへんかな」と思いましたが、
そのたびに、久保先生の講義や話されたことを思いだして、何とか頑張りました。
久保先生、ありがとうございました。
たいへん感謝しております。

2020年02月08日
合格体験記 9 (下)
[前回からの続き]
■試験当日の迎え方
試験会場が清水西高校だったため、実際の交通機関を使って事前に下見に行きました。
学校の前まで歩き、駅からの順路や学校の入口も確認しておきました。
当日の試験までの時間をどう過ごすかを考え、会場近くの図書館も下見し、
実際に自習スペースを事前に使用しました。
試験前日と当日は、上述の「要点整理テキスト」の付箋箇所と”あんちょこ”を全部
見直しました。
当日会場に持参するテキストも、この2つに絞り込みました。”あんちょこ”は、先生の
統計情報のプリントと一緒にポケットファイルにつづって持参しました。
■SBS学苑を選択した理由
SBS学苑を候補にしたきっかけは、費用と奨学金制度という、コスト面での魅力でした。
とりあえず「無料ガイダンス」に参加しましたが、初対面の久保先生の、たいへん熱心で
非常に聞き取りやすく心地の良い語り口に、すっかり惹きつけられ、
「久保先生の講義を受ければ、私でも<一発合格>できるかも知れない…」と、
心を突き動かされ、SBS学苑に即決しました。
私が一番大切にしたのは、「先生に言われたことは、必ず取り組む!!」ことです。
①1年間の目標を立てること
⇒<一発合格>して奨学金をゲットして、コートを買う目標を立てました。
皆勤+模試基準クリア+合格により、本当にご褒美にコートを購入することができました。
②月初めの目標を立てること
⇒3月の目標は「自分なりの学習方法を確立すること」だけ、など、月単位で無理のない
目標を立てることで達成感を味わえ、現在の立ち位置(=すべきこと)を意識しながら
取り組むことができました。
③好きなことを我慢して臨むこと
⇒お盆休みを最後に、好きなお酒を完全に断ちました。
④学習スケジュールを立てること
⇒スケジュール帳に毎日の学習内容、学習時間、今週中にやるべきこと、今月中に
やるべきこと…などを書き込みました。
他にもプリントを貼る、とかブログを読むとか、先生のご指示は誰でも無理なくできる
簡単なことですが、後回しにしたら絶対に面倒になる自分の性格上、
この講座のことだけは真っ先に取り組もうと決めていました。
合格後も先生の指導を守り、登録実務講習もすぐに受講し、登録申請も済ませ
「本当の意味での宅建士になれた」ことを実感できる日を、晴れ晴れした気持ちで
待ち望むことができています。
■最後に
宅建業界と無縁の世界で、取り柄もなく毎日の生活に流されるだけだった自分が
「宅建士」になれたのは、すべて久保先生のおかげです。
SBS学苑で講座を受講していなかったら、<一発合格>する覚悟も、試験当日
最後の1分まで諦めずに戦う信念も、自分の中に芽生えることはなかったと思います。
「”令和” 最初の宅建士になりましょう!」
「残りの人生〇十年間、ずっと、『宅建持ってて、すごいね!』って言われましょう!」
…先生の下さった激励の言葉に、これまでの自分の中にはなかった熱量を注入されました。
思い返せば、正直苦しい日々でしたが、自分を信じて完走できたことを、
心から感謝しています。
本当にありがとうございました。

2020年02月07日
合格体験記 9(中)
[前回からの続き]
■各科目の学習方法(復習方法)
<権利関係>
権利関係(特に民法)は、とにかく慣れるのに時間がかかりました
(結局、ようやく馴染んだのは物権が終わる6月頃でした)。講義がどんどん
進んでしまう中で、常に先生の「まず森を見よ」の言葉を意識し、全体の理解を
見失ったまま進捗してしまわないよう、早めに復習に取り掛かりました。
また、解らない箇所(特にせっかく過去問を解いても、「解説」が未履修の単元を
含め説明していて、意味が全く理解できないことが多かったです)があれば、
その日のうちに先生にメールで質問させていただきました。
先生が即時に解説して下さり、お忙しい中、お電話で対応して下さることも何度も
ありました。おかげさまで、最終的には民法が得意科目になり、直前模試では
14問中13点を取ることができました。
具体的な復習方法は、①頻度表に合わせた見直し②自分の苦手単元の見直し
の2巡が必要でした。
①は、過去問の解き直しをしました。時期は、ゴールデンウィークで、講義がお休みに
なった期間、先生からいただいた頻度表中の5年以上/10年中に絞り込みました。
②は、テキストの読み直し・精読+もう一度 講義の聴き直しをしました。
通常の講義の進捗が終盤に差し掛かる上で、もう一度 原点回帰できたため、
単元と単元が結びつき、ここで初めて「木を見て、森を見られた」実感がありました。
時期は6月中旬~8月にかけて取り組みました。
<宅建業法>
内容の理解に苦慮する民法とは異なり、講義の中である程度身についた実感があった
こと、また、合格の得点源になる科目として違った訓練が必要だったことから、再度の
インプットは行わず、アウトプットに徹しました。講義の進捗と並行した毎週の復習に使う
過去問題集に、LECのものを1冊加え、翌週の講義までの間で、ある程度の状態まで
もって行けるようにしたつもりでした。
しかしながら 9月の答練では、13/20点しか取れず、たいへん焦りました。
もはや直前期にインプットにかけられる時間は限られ、テキストを頭から読み直す余裕は
ないため、最重要頻出ながら理解できていると思い込んでいた箇所(特に35条と37条、
免許と登録)に絞り込みをし、いわゆる”あんちょこ”を作りました。
ダイニングテーブルのマットに挟み込み、しょっちゅう見ることで、視覚から叩き込む
インプット方法をとりました。
<法令上の制限/税法/その他>
秋口の講義であるタイミング上、業法以上に直前期までに もう一度見直しをする余裕は
ありませんでした。それを覚悟した上で毎週の講義に臨み、1週間の復習の中で
落とし込みをおよそ完結できるようにしました。
「要点整理テキスト」を見直してみると、過去問の解説などから拾い出して、テキストに
自分で書き込んだメモ書きが一番多かった科目でした。
■直前期の勉強方法
「答案練習 Ⅰ」(9月24日)を控え、その1週間前からは本番に向けた訓練に集中することに
決めていました。市販の予想問題集を8冊購入し、毎日必ず1回分、時間を計って途中で
区切ることなく解きました。初めて解いた日は「これで全く得点できなかったらどうしよう…」
と本当に不安でしたが、答練当日までの1週間でもコンスタントに35点前後取れていました。
解き進める科目の順番や、時間配分、筆記用具も本番仕様に揃え、それなりに自信を持って
挑んだ「答練 Ⅰ」当日、本番さながらの緊張感に、想定外にも飲みこまれてしまい、
全く普段通りに解くことができませんでした。結果は28点、業法は13点。正直、ショックで
茫然としましたが、立ち止まる暇はない中で確信はありませんでしたが、このまま予想問題
1日1回分を続けることを主軸にし、宅建業法だけは過去問題集を40分間で解くことを
加えました。最終的に試験前々日までに30回以上、予想問題に取り組むことができ、
宅建業法も、最低17/20点まで水準を上げることができました。
加えて、予想問題集で間違えたところや知らなかった知識を「要点整理テキスト」に
落とし込んでいく作業を加えました。テキストを見直すと、書いてあるのに読み飛ばしていた
ことが多く、マーカー+付箋をしました。記載がなければ、手で書き込む時間さえも
惜しかったため、解説集を40%程度にコピーし、テキストの該当箇所にペタペタと貼りつけ
+付箋をしました(この付箋が、試験当日までの指標・宝になりました!)。 (続 く)

2020年02月06日
合格体験記 9(上)
合格体験記
SBS学苑 パルシェ校 N.K さん(静岡市 30歳代 女性)
■「宅建士」を目指したきっかけ
私は、息子の小学校入学に合わせて、昨年退職しました。電車とバスを
乗り継いでの通勤に片道2時間・・・家族の協力なしには働けませんでしたが、
「子どもの帰りを、家で待ってあげて欲しい」という主人の想いに応え、
決断したとは言え、やはり不本意な退職になってしまったので、
母親である女性でも、何度でも人生を立て直すことができることを証明したい…
と奮起し、「宅建士」を志しました。
いずれまた家族の事情で仕事を辞めることになったとしても、資格さえあれば
今度は独立開業の道が残るということも決め手でした。
専業主婦としてスタートしたため、勉強時間を確保できるアドバンテージが
ありましたが、学習ペースをつかみかけた矢先、突然義母が要介護になりました。
介護サービスの調整や入退院や通院と、思いもしなかった負担がのしかかり、
正直 悔しくてたまらず…それでも、これで失敗して家族を責めることだけは
したくないと、意地でも絶対「一発合格」するのだと、決意を新たにする契機に
なりました。
また、自分には十分時間があるという慢心を早々に捨て、いつ何が起きて
予定を狂わされるかわからないという焦りを持って学習を進める緊張感に
つながりました。
■学習時間
・平日⇒朝8時から子供が帰宅するまで
・子供の休日⇒朝4時から子供が起床するまで
子供がいる時間は子供に集中、基本的には勉強しないことに
潔く決めていました。子供がいれば計画通りに進まず、手を止めることになり、
苛々するだけなので、思い切って諦めてメリハリをつけたことで、子育てと
両立することができました。
ただし、子供との時間でもスキマに勉強時間を見つければ、集中することにし、
習い事や美容院に連れて行った際の待ち時間や、家でも子供がテレビに
没頭してくれている時間だけでも、相当な時間を捻出することができました。
夏は子供の長い夏休みにのまれて、ペースを見失うことのないよう、23時までに
就寝、朝3時に起床し勉強する朝活中心の生活リズムに切り替えて乗り切りました。
泊りがけの家族旅行にも行きましたが、旅行先でも朝活は欠かさずにこなしました。
■1週間の学習方法(講義~次の講義まで)
(1)予習
新鮮な疑問を持って講義を受けられるよう、あえて当日に行い、不明な箇所に
付箋を貼りました。
(2)復習
①講義の聴き直し
ICレコーダーで、もう一度 講義をすべて聴き直しました。講義内で聞き漏らし、
もう一度聞きたいと特に思う箇所は、レコーダーのタイマーの時間をテキスト隅に
メモしておき、聴き直しの時には理解できるよう、注意して聴き直しました。
②ノート作り
(先生は「ノート作り不要」とおっしゃっていたのですが…)まとめるためのノートではなく、
書くことで記憶するためだけのノートとして作成しました(試験までに見直しすることは
やはりほとんどありませんでした)。
③過去問
先生が推薦された中から、日建学院とTACの2冊を選択しました。初学者にとって
講義序盤の民法の頃は、講義1回分だけで取り組める問題数が限られてしまうため、
初めから2冊を併用しました。1回の講義分で2冊合わせて30~50問(重複含めて)
程度、問題数をこなすことができました。
④一問一答
住宅新報社を選びました。
一問一答は解きやすく正答も出しやすいですが、過去問に取り組んでから一問一答を
解くと最終的な確認にもなり、何より自信が取り戻せてモチベーションアップになりました。
⑤過去問と一問一答で間違えた箇所の解き直し
一巡目で×がついた問題はもう一度解き直しました。
2度解いても正解できない問題には後日復習できるよう、付箋を貼っておきました。
⑥先生のブログ精読
次回講義前に、前回講義の要点まとめの記事を出して下さるので毎回印刷していました。
これを先生から出された「記述問題」だと想定して、自分の言葉で文章で回答できるか
書いてみることで、理解度のチェックができました。(続 く)