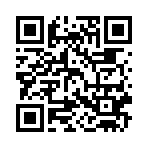2019年01月31日
合格者へのインタビューⅡ
平成30年度の「宅建試験」に合格された受講生に、
資格を目指した動機や学習方法についてうかがいました。
彼女は現在、高校生と保育園児の、2人の男の子のお母さんで、
最初のご受講は2010年でした。
それから足かけ8年。受験しなかった年もあるようですが、
この間、仕事と子育てを両立させながら、あきらめなかった、
この気持ちの強さ を、ぜひ皆さんに知っていただきたいと思います。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SBS学苑 沼津校 A.U さん(函南町 30歳代 女性)
(Q1)「宅建」を取ろうと思った動機はなんですか?
(A1)夫の両親が不動産を所有しており、宅地建物に関する知識習得のため、
すすめられたのがきっかけでした。
(Q2)お仕事や育児で忙しかったと思いますが、どのようにして勉強時間を
確保しましたか?
(A2)仕事の休憩時間/育児や家事が終わる23時頃から0時半頃まで
部屋にこもった/休日は時間を決めて図書館で勉強 しました。
(Q3)SBS学苑の講座に通って良かった点は何ですか?
(A3)1週間に一度だけでも、宅建の勉強に集中することができ、同じ目標を持った
人たちと同じ空間にいることで、自分のモチベーションも上がりました。
(Q4)受験期間中に、つらかったことは何ですか?
(A4)フルタイムで仕事をし、育児・家事をしながら、ひと段落した23時頃からの
勉強は、睡魔との戦いでした。
(Q5)「合格」した、今のお気持ちを教えて下さい。
(A5)負けず嫌いな性格のため、最初は家族のすすめで始めた資格取得でしたが、
いつの間にか「自分のための勉強」という風に気持ちが変わっていました。
何度も失敗し、そのたびにくじけそうになりましたが、周囲からの応援もいただき、
気持ちを奮い立たせて頑張ってきて本当に良かったです。試験当日の解答速報
の自己採点では、ギリギリのラインだったので、合格発表日まで毎日、
落ち着かない日々を過ごしてきましたが、合格通知が届いたときは、
涙が出るほどうれしかったです。
何年かかっても、自分が決めた目標を達成できたことが自分の誇りです。
(Q6)あとに続く受験生に対して、ひと言お願いします。
(A6)何年かかっても、自分の決めた目標をあきらめることなく頑張って欲しいです。
家事や育児や仕事に追われていても、ほんの少しの時間を大切にすることで、
努力は必ず報われます。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[講師より]
彼女は、受講初年度も、模擬試験の成績が悪かったわけではなく、
「あと少しで合格圏」という実力はありました。
にもかかわらず、合格まで8年を要したというのは、やはり他の受験生に比べて
勉強時間の確保が難しかったことにあると思います。
しかしその困難を乗り越えて、この栄冠を手にされた根性に敬服します。
皆さんも、資格取得まではあきらめずに、とことん食らいついて行きましょう!

2019年01月29日
再受講を検討されている方へ
いよいよ、SBS学苑「宅建士合格講座」の開講が迫ってきました。
過去に私の講座をお受けいただいた方の中には、
「再受講をしようか」迷っていらっしゃる方もおられると思います。
そのような方に、私はこうお伝えしたいです。
「今年、絶対に合格するために、もう一度、一緒にがんばりましょう!」
10月の本試験までは、長丁場です。
そこで、まず必要なのは、 「ペースメーカー」です。
今 お持ちのモチベーションを維持しつつ、本試験で最高の実力を発揮できるように、
週1回の講義を受けに来て下さい。
そこで、いつものように私があなたを ”叱咤激励” します。
テキストはこれまでとほぼ同じですので、
内容的に新味はないと思いますのが、
あなた自身の理解力が、これまでとは違っているはずです。
結局は、今年受かればいいのです。
「再受講は恥ずかしい」なんていうことは考えなくても結構です。
なぜなら、それはあなたの人生であって、
自分に正直に、わがままであるべきだからです。
受かれば、確実に人生が変わります。
もう一度言います。 ご一緒にやりましょう。 お待ちしております。
[受講を決められた方は、恐れ入りますが、すぐにSBS学苑までご連絡下さい。]
http://www.sbsgakuen.com/

2019年01月27日
民法のいわゆる「2020年問題」
一昨年(2017年)6月2日に、民法の一部を改正する法律が公布され、
施行日が、2020年4月1日に決まりました。
宅建試験は、試験年の4月1日現在施行されている法令から出題されるため、
今年(2019年)は、現行民法からの出題ですが、
来年(2020年)は、改正民法(債権関係:改正項目は約200項目)からの
出題であると思われます。 ※
※ 正式には、指定試験機関である「不動産適正取引推進機構」の発表を
待たなければならない。
もし、2020年の民法が、改正法からの出題だとすると、
民法は(今のままの配点であれば)10問分出題されますので、
直接的には10点分に影響が出てくるということです※。
※ただし、借地借家法などとの複合問題では、それ以上になりうる。
2020年から「宅建」を学習される方は、
市販のテキストも、改正民法での記述になっており問題はありませんが、
既に何回か受験されている方は、
改正民法部分を学び直さなければならないということになります。
従って、最もシンプルな考え方としては、
「今年、絶対に受かるしかない」ということになります。
受験生の皆さん、一度「宅建合格」を目指したからには、
必ず最後は「合格」で終わりましょう!
私がいつも言うように、宅建は、
「合格するか、あきらめるか」の試験なのです。

2019年01月22日
できれば開講前に読んでおきたい本
3月の「宅建士合格講座」開講が近づいてまいりました。
その「合格講座」第1回目の「宅建概論」でもお話ししますが、
皆さんとは最初に、民法を学習するということもあり、
事前にぜひ読んでおいていただきたいテキストがあります。
それは、伊藤 真(著) 「伊藤 真の民法入門」(日本評論社)です。
伊藤 真(まこと)氏は、言わずと知れたLEC創成期の司法試験部門を
作り上げた方で、法律系国家資格指導の第一人者です。
現在は、護憲派弁護士としても活躍されていますね。
民法は、我々の日常生活に密接な関係のある、非常に重要な法律です。
法律上の「人」とは何かから始まり、
契約(売買や賃貸借)・債務不履行・連帯保証・
抵当権・時効・相続等、ビジネスでも有用な知識を学習します。
ただ、我々が講座で使うテキストが、
(当たり前ですが)受験対策として書かれたテキストのため、
ともすると、とっつきにくく、
本来ならおもしろく、ためになるはずの民法の良さが
伝わりにくい恐れがあります。
そこで、この「民法入門」を事前に読んでおけば、比較的スムーズに、
民法のおもしろさを理解していただけると思うのです。
「民法入門」は口語体で書かれているため、
170ページほどの分量ですが、一気に読めてしまいますよ。
さあ、皆さん、今すぐ大きな書店あるいはアマゾンにて、
この本を手に入れて下さい!
(アマゾンだと、旧版の中古は1円で出ています!旧版でじゅうぶんです)
そして、法律学習の”核”である民法を、好きになりましょう!

2019年01月16日
「宅建士合格講座」の特長
私が講師を務めております、SBS学苑「宅建士合格講座」には
次のような特長があります。
1 ライブ授業であること(他校さんは、DVD授業であることが多いです)。
2 授業の前や後、講師にその場で質問ができること。
3 欠席・遅刻・早退をした方のために、「無料貸し出しDVD」があること。
4 SBS学苑独自の奨学金制度(最大で受講料の50%バック)があること。
5 受講料が比較的リーズナブルであること(受講料+教材費で10万円以内)。
※宅建協会会員業者の従業者様には、さらに割引特典あり
さらに付け加えるなら、事務局の皆さんの対応が素晴らしいです(これ大事です!)。
私は、自信を持って、この講座をおすすめ致します。
今年、受験をお考えの方は、ぜひ〈無料ガイダンス〉にお越し下さい(要予約)
日程:パルシェ校:2/12(火)・イーラde沼津校:2/14(木)・遠鉄校:2/15(金)

2019年01月07日
「宅建士合格講座」のご案内
今年も、SBS学苑にて「宅建士合格講座」を開講致します。
例年、数多くの合格者を輩出している、歴史と伝統のある講座です。
さあ、あなたも、この講座に通って「合格」の栄冠を手にしましょう!
http://www.sbsgakuen.com/Detail?gakuno=2&kikanno=192379
※ 講師から学苑への紹介の場合、受講生に「特典」がありますので、
お知り合いにこの講座をご紹介下さる場合は、
まずは久保までご連絡下さい(054-653-0535)。
[開講日]
パルシェ校 (☎054-253-1221):2019年3月5日(火) 19:00~21:00
イーラde沼津校 (☎055-963-5252):2019年3月7日(木) 18:30~20:30
遠 鉄 校 (☎053-455-2230):2019年3月8日(金) 18:30~20:30
[無料ガイダンス]
パルシェ校:1/15(火)・イーラde沼津校:1/17(木)・遠鉄校:1/18(金)
※詳しくは、学苑各事務局までお問い合わせ下さい。

2019年01月05日
合格体験記 (後編)
(SBS学苑 パルシェ校 M.T さん 藤枝市 53歳 男性)
(前編)からの続き
■教材
SBS学苑で指定された「基本書(テキスト)」、「分野別過去問題集」と、
「過去問10年間」と「要点整理テキスト」が中心で、基本的にその他の教材に
手を出すことはしませんでした。
あれこれ手を出すよりも、1つの教材に集中するほうが良いと考えています。
ただ、電車の通勤時間やすきま時間を有効活用するため、スマホのアプリは
活用しました。
「スタケン」はよくできていると思います。
その他、TACの「直前予想問題(3回分)」は購入しましたが、時間不足で
2回分しかできませんでした。
「要点整理テキスト」は、早い段階で購入したもののあまり活用しませんでした。
しかし、宅建業法の35、37条の理解に苦労している時、「要点整理テキスト」を
確認したところ、たいへん有効であることに気づきました。
その他にも、免許や建築基準法など多くの論点で役立つと思います。
もっと早くから使えばよかったと思っています。
■講義
当初は、自身のペースメーカーと考えていましたが、勉強に取り組むうちに
精神的な支えになっていたように思います。
9月下旬の重要な時期に、勉強時間が思うように確保できず、
集中力も途切れることが多くあり、何度も今年度の合格をあきらめかけました。
しかし、講義を受けるたびに気を取り直すことができ、続けることができました。
久保先生の熱心な講義と他の受講生が作る真剣な雰囲気のおかげだったと
思います。仮に独学だったならば、いろいろな言い訳のもとに、
あきらめていただろうと思います。
■心がまえ
今回、運よく合格とはなりましたが、いくつかのラッキーがあったことも事実です。
ただ、勉強の過程と試験のその時まであきらめなかったことが、
ラッキーにつながったと思っています。
特に、試験直前期まで、「統計問題と権利関係の判例問題は捨てよう」と
考えていましたが、統計問題は前日に各情報を暗記し、
判例問題は捨てることをせずに解答しました。
結果、この2問の正解があったことから合格点を超えることができました。
大きなポイントとなったと思います。
最後の最後まで、「あきらめないこと」が大切です。
■最後に
8ヶ月間、久保先生にはたいへんお世話になりました。
頻度表に基づく、重要論点に集中した授業で無駄なく進めてもらい、
時折りある「覚え方」は、実際に出題され(今回の問2)、得点できました。
また、3人の受講生の方にも懇意にしていただき、皆さんの勉強の進度や
自分の遅れの程度など、励みや刺激になりました。
ともに、たいへんありがとうございました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[講師より]
Tさんの受講時の集中力の高さは、私の講義中にもしひしと
伝わってきました。
それはきっと、しっかりと予習をされていたからこその、
事前知識(情報)との整合化を図る作業を、脳内でやっていらしたんですね。
お勤め・兼業・プライベートと多忙な中で、いかに学習時間を捻出し、
効率よく知識を定着させていくかということに腐心されたさまがよくわかりました。
その点が特に、後進の皆さんの役に立つだろうと思います。
本当に「合格」おめでとうございました!

2019年01月04日
合格体験記 (前編)
仲間と励まし合いながら、気持ちを途切らさずに前へ進んだ
(SBS学苑 パルシェ校 M.T さん 藤枝市 53歳 男性)
■受験の動機と環境
私は53歳、金融機関の関連会社社員で、定年退職後を何となく意識する中で、
今後の生き方を考え、宅建取得を決意し、今年度チャレンジしました。
私は通常、残業が7~8時まであり、その後に週2~3回は飲み会が入ります。
土日等休日は兼業する農業に取り組み、また、子供の学校の部活動の
おつきあいも必須という環境にありました。
加えて、9月から10月初旬は、近隣神社のお祭りの準備と祭典にかり出され、
また、子供の部活動の合宿への帯同など、「勉強時間」という意味では、
たいへん厳しい環境にありました。
■勉強時間の確保
私は電車で通勤していますが、往復約35分の車中は貴重な勉強時間でした。
加えて、朝7時20分には出勤し、始業までの約1時間と、
飲み会の有無にかかわらず、帰宅後毎日1時間は欠かさず勉強しました。
土日等休日も帰宅後3時間程度勉強時間を確保しました。
毎日欠かさず3時間前後(9月下旬頃からは4~5時間)の勉強をしてきました。
また、すきま時間も有効に活用してきました。
■勉強方法
パルシェ校の講座は火曜日のため、日・月曜日は予習、
その他は過去問を中心とした復習に徹しました。
火曜日の授業を理解し、有意義にするため、予習は必ずしました。
予習はテキストを2~3回程度読み、過去にどんな出題がされているか、
簡単にチェックし、講義に臨みました。
復習は徹底的に過去問に取り組み、その解説をくまなく読み込みました。
過去問の解説には理解を深める情報や、他の問題に関連する情報が
たくさん含まれています。
そのため過去問の解説は、既に理解できている内容であっても徹底して
読みましたし、過去問解答時にはそれぞれの選択肢がなぜ正解なのか、
どこが間違っているのかを自身に説明しながら解答を重ねました。
また、「一度間違えた問題は、必ずまた間違える」と考え、
間違えた問題は何度も何度も繰り返し解きました。
(後編)へつづく