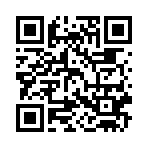2025年03月24日
本試験に”再挑戦”される方へ
「宅建試験」は、今や難関試験です。
だからこそ、価値があるのですが、複数回受験することとなった方は、
初学者の時とはまた違った、学習方法の工夫が必要になってきます。
私は、基本となる学習方法として、
①ペースメイク
②テキストの読み込み
③過去問演習
の3本柱を挙げていますが、
再挑戦の場合には、これに各々アレンジをして行かなければなりません。
例えば、
①・・・もし、通学講座に通わないのであれば、何月ごろから学習をはじめたらいいか、
現在のご自分の実力と相談して、スタート時期を決めるべきです。
(基礎力があるのであれば、6~7月頃からのスタートで大丈夫でしょう)
②・・・まずは、ご自分の弱点である項目(「契約不適合責任」とか「抵当権」とか)を
書き出し、ネット等を活用して、これまで使っていたテキストとは違う表現の
解説や具体例に触れてみることで、新たな発見があるかも知れません。
③・・・一般的には、「四肢択一」の過去問を解くことが過去問演習ですが、
今後は「一問一答式」による過去問学習をおすすめします。
これにより、「四肢択一」の演習では可能だった、消去法を使って正答を導くことが
できなくなりますので、より精度の高い知識を習得するきっかけになるでしょう。

だからこそ、価値があるのですが、複数回受験することとなった方は、
初学者の時とはまた違った、学習方法の工夫が必要になってきます。
私は、基本となる学習方法として、
①ペースメイク
②テキストの読み込み
③過去問演習
の3本柱を挙げていますが、
再挑戦の場合には、これに各々アレンジをして行かなければなりません。
例えば、
①・・・もし、通学講座に通わないのであれば、何月ごろから学習をはじめたらいいか、
現在のご自分の実力と相談して、スタート時期を決めるべきです。
(基礎力があるのであれば、6~7月頃からのスタートで大丈夫でしょう)
②・・・まずは、ご自分の弱点である項目(「契約不適合責任」とか「抵当権」とか)を
書き出し、ネット等を活用して、これまで使っていたテキストとは違う表現の
解説や具体例に触れてみることで、新たな発見があるかも知れません。
③・・・一般的には、「四肢択一」の過去問を解くことが過去問演習ですが、
今後は「一問一答式」による過去問学習をおすすめします。
これにより、「四肢択一」の演習では可能だった、消去法を使って正答を導くことが
できなくなりますので、より精度の高い知識を習得するきっかけになるでしょう。
また、「教材にかけるお金」ですが、問題集やサブテキストなど、
トータルで1~2万円くらいは、悩まずに投資しましょう。
「再受講」の数万円も、惜しむべきではありません。
なぜなら、あなたが「合格」すれば、そのお金は数百、数千倍になって返ってくるからです。
その程度の自己投資にビクビクしているようでは、大きな果実は手に入りません。
宅建は、「受かるか、受からないか」ではなく、「受かるか、あきらめるか」です。
「宅建試験合格」を志した以上、受かるまでやるべき です。
さあ、残された時間は”ある”ようでいて、それほど”ありません”。
宅建は、「受かるか、受からないか」ではなく、「受かるか、あきらめるか」です。
「宅建試験合格」を志した以上、受かるまでやるべき です。
さあ、残された時間は”ある”ようでいて、それほど”ありません”。
頂上に向けて、充実した日々を送りましょう!

2025年03月23日
わからないことは、すぐに調べよう!
初めて「宅建試験」の学習をすると、

今まで見聞きしたことのない、膨大な量の情報、
特に「法律用語」や「法的思考(法的ものの考え方)」に直面することになります。
そして、「合格」するためには、それらを理解し、整理し、扱(あつか)えることが要求されます。
しかし、それはもちろん一朝一夕にできることではないので、
日々の生活の中において、少しずつでもクリアしていかなければなりません。
そこで皆さんにお勧めしたいのは、
わからないことが出てきたら、できるだけ速やかに「調べる」クセをつけることです。
今は、わざわざ図書館に行ったり、書籍を購入したりしなくても、
スマホやPCで、すぐに検索できる便利な世の中になりました。
ですから、今のうちから少しずつでも、
すぐにものを「調べる」クセをつけて、知識を集積して行きましょう。
特にお勧めなのは、「画像検索」です。
難しい概念も、図表やイラスト化されたものが出回っていますので、
そちらを利活用して、どんどん理解を深めていきましょう!
そんなことを、8月9月にやっていては遅すぎます。
すぐに調べることで、ストレスなく、楽しみながら
「合格」に近づいて行きましょう!

2025年03月20日
「過去問到達度 チェックシート」の効用
皆さんにお配りした「過去問到達度 チェックシート」の効用を確認しましょう。

1. 自分がそれまでに何問解いたのか、それをいつ解いたのか等を記録できる。
2. 解いた問題数が増えていくことがやりがいになる。
3. 講師に進度を確認してもらうことでアドバイスを受けやすい。
等が挙げられます。
テキストを読んでいる(インプット)だけでは、 「知識」は脳に定着しません。
テキストを読んで、「知識」をチャージ(充電)したあとは、
自分がそれを理解しているかどうかを、問題演習によって検証する必要があります
(アウトプット)。
すべては、あなたの「合格」のためです。
さあ、毎日 一問でも二問でも解いて、先へ進みましょう!
2. 解いた問題数が増えていくことがやりがいになる。
3. 講師に進度を確認してもらうことでアドバイスを受けやすい。
等が挙げられます。
テキストを読んでいる(インプット)だけでは、 「知識」は脳に定着しません。
テキストを読んで、「知識」をチャージ(充電)したあとは、
自分がそれを理解しているかどうかを、問題演習によって検証する必要があります
(アウトプット)。
すべては、あなたの「合格」のためです。
さあ、毎日 一問でも二問でも解いて、先へ進みましょう!
はじめから「チェックシート」を使っておかないと、のちのち後悔します。
その継続の先に、「合格」があります!
その継続の先に、「合格」があります!

2025年03月14日
[保存版] 民法と宅建業法の関連事項
「民法」は、のちに学習する「宅建業法」と深いつながりがありますので、
「民法」を学習する今のうちから、「宅建業法」を射程範囲内に入れて、
意識しておくことが重要です。

「民法」を学習する今のうちから、「宅建業法」を射程範囲内に入れて、
意識しておくことが重要です。
※このブログはプリントして、テキストの適当な箇所に貼りつけておきましょう。
[凡例]
■「民法」の項目(民法典の位置づけ:基本書の頁)⇒「宅建業法」の項目:基本書の頁
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
■制限行為能力者(総則:5)⇒免許の基準:304/登録の基準:312
■未成年者(総則:6) ⇒専任の宅建士:294/免許の基準:304
/登録の基準:312
[凡例]
■「民法」の項目(民法典の位置づけ:基本書の頁)⇒「宅建業法」の項目:基本書の頁
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
■制限行為能力者(総則:5)⇒免許の基準:304/登録の基準:312
■未成年者(総則:6) ⇒専任の宅建士:294/免許の基準:304
/登録の基準:312
■条件(総則:46) ⇒自己の所有に属しない...売買契約締結等の制限:355
■損害賠償額の予定(債権:128)⇒重要事項説明:340/契約書の交付:350
■損害賠償額の予定(債権:128)⇒重要事項説明:340/契約書の交付:350
/損害賠償額の予定等の制限:360
■契約の解除(債権:129) ⇒重要事項説明:340/契約書の交付:350
■手付金(債権:134) ⇒重要事項説明:340/手付貸与の禁止:380
/契約書の交付:350/手付の額の制限等:361
/手付金等の保全:364
■危険負担(債権:137) ⇒契約書の交付:350
■売主の契約不適合責任(債権:139)⇒契約書の交付:350
/担保責任についての特約の制限:362
/契約書の交付:350/手付の額の制限等:361
/手付金等の保全:364
■危険負担(債権:137) ⇒契約書の交付:350
■売主の契約不適合責任(債権:139)⇒契約書の交付:350
/担保責任についての特約の制限:362
■他人物売買(債権:140) ⇒自己の所有に属しない...契約締結等の制限:355

2025年03月13日
「問題集」の特性・使用時期・活用法
さて、宅建に限らず、資格試験攻略のためには
「過去問学習」が必須なのですが、
市販されている問題集にはそれぞれ特性があります。
その特性をじゅうぶん理解した上で、効率的な学習をしましょう。
「分野別 過去問題集」
・学習の導入部から本試験直前まで、最も長い期間使用できる問題集です。
・授業内容の復習⇒知識の定着、弱点補強と、実力アップのために欠かせません。
・「過去問」ですので、<問題>自体はどの出版社のものでも同じですが、
<解説>は出版元によって、その質に大きな違いがありますので、選定の際には
留意しましょう。
「50問ワンセットになった過去問題集」
・主として、8月から試験直前までに使用する問題集です。
・ひと通りのインプットが終った後に、「2時間の試験時間をどのように使うか」、
また、「総合的にどれだけの実力がついたか」を測るために使います。
・気をつけたいのは、古い問題から新しい問題という流れで解くべきだということです。
〇 H22⇨R5
× R5⇨H22
これは、ご承知のように、新しい問題ほど長文化しており、難易度が高いからです。
「一問一答式 過去問題集」
・四肢択一の問題は、「必ずどれかが正解だ」という逃げ道がありますが、
一問一答の場合は、それがありませんので、知識の精度を高めるのに最適です。
・ひと通り四肢択一をやりつくした方や、お仕事の合間のこま切れの時間を
活用したい方に向いている問題集だと言えるでしょう。
「予想問題集・模擬試験」
・もちろん、9月以降の直前期に使うべきものですが、
注意したいのは、これらに登載されている問題はあくまでも「新作」問題ですので、

「過去問学習」が必須なのですが、
市販されている問題集にはそれぞれ特性があります。
その特性をじゅうぶん理解した上で、効率的な学習をしましょう。
「分野別 過去問題集」
・学習の導入部から本試験直前まで、最も長い期間使用できる問題集です。
・授業内容の復習⇒知識の定着、弱点補強と、実力アップのために欠かせません。
・「過去問」ですので、<問題>自体はどの出版社のものでも同じですが、
<解説>は出版元によって、その質に大きな違いがありますので、選定の際には
留意しましょう。
「50問ワンセットになった過去問題集」
・主として、8月から試験直前までに使用する問題集です。
・ひと通りのインプットが終った後に、「2時間の試験時間をどのように使うか」、
また、「総合的にどれだけの実力がついたか」を測るために使います。
・気をつけたいのは、古い問題から新しい問題という流れで解くべきだということです。
〇 H22⇨R5
× R5⇨H22
これは、ご承知のように、新しい問題ほど長文化しており、難易度が高いからです。
「一問一答式 過去問題集」
・四肢択一の問題は、「必ずどれかが正解だ」という逃げ道がありますが、
一問一答の場合は、それがありませんので、知識の精度を高めるのに最適です。
・ひと通り四肢択一をやりつくした方や、お仕事の合間のこま切れの時間を
活用したい方に向いている問題集だと言えるでしょう。
「予想問題集・模擬試験」
・もちろん、9月以降の直前期に使うべきものですが、
注意したいのは、これらに登載されている問題はあくまでも「新作」問題ですので、
過去問の質には及びません。
したがって、過去問をじゅうぶんにやり尽くしてから、
本試験直前のコンディション調整や、ご自分の新たな弱点を見つける目的で
使って下さい。
さあ、いよいよ開講しましたので、
したがって、過去問をじゅうぶんにやり尽くしてから、
本試験直前のコンディション調整や、ご自分の新たな弱点を見つける目的で
使って下さい。
さあ、いよいよ開講しましたので、
初学者の方は授業の進度に合わせて、どんどん過去問を解いて行きましょう!

2025年03月12日
「税法」「その他の分野」の学習について
第1回目の講義でも申し上げましたが、
「税法」と「その他の分野」の学習については、次の取り扱いでお願い致します
(いずれも初学者の方に対してです。1度でも受験した方にはあてはまりません)。
■「税法」
9月に1コマ(2時間)の授業がありますが、
それまで過去問を解く必要はありません。
ただ、読みもの的にテキストの該当箇所をななめ読みするのは構いません。
なぜなら、9月にならないと、正確な法改正情報にのっとった学習ができないため、
法改正前の古い過去問を解いても意味がないからです。
授業が終わったら、一気に学習しましょう。それで十分間に合います。
■「その他の分野」
(土地の性質)(建物の性質)(住宅金融支援機構法)(景品表示法)(統計)
の5問分と、(不動産鑑定評価基準)(地価公示法)を指します。
7月に1コマ(2時間)の授業がありますが、
5問免除の方は、後の2項目のみの、その以外の方は全7項目の、
テキスト読みと過去問演習を、ご自分で3月からコツコツとやり進めていって下さい。 これら項目については、「民法」のような、法解釈論的な学習は必要ないため、
少なくとも過去に出題された範囲内については、一人で学習を進めていけるからです。
従って、7月の授業が、皆さんにとっての復習になるようなかたちが望ましいです。

「税法」と「その他の分野」の学習については、次の取り扱いでお願い致します
(いずれも初学者の方に対してです。1度でも受験した方にはあてはまりません)。
■「税法」
9月に1コマ(2時間)の授業がありますが、
それまで過去問を解く必要はありません。
ただ、読みもの的にテキストの該当箇所をななめ読みするのは構いません。
なぜなら、9月にならないと、正確な法改正情報にのっとった学習ができないため、
法改正前の古い過去問を解いても意味がないからです。
授業が終わったら、一気に学習しましょう。それで十分間に合います。
■「その他の分野」
(土地の性質)(建物の性質)(住宅金融支援機構法)(景品表示法)(統計)
の5問分と、(不動産鑑定評価基準)(地価公示法)を指します。
7月に1コマ(2時間)の授業がありますが、
5問免除の方は、後の2項目のみの、その以外の方は全7項目の、
テキスト読みと過去問演習を、ご自分で3月からコツコツとやり進めていって下さい。 これら項目については、「民法」のような、法解釈論的な学習は必要ないため、
少なくとも過去に出題された範囲内については、一人で学習を進めていけるからです。
従って、7月の授業が、皆さんにとっての復習になるようなかたちが望ましいです。
以上、よろしくお願い申し上げます。

2025年03月11日
「過去問演習」の方法
さて、「合格」に向けて注力しなければならない「過去問演習」ですが、
初学者の方は、そもそもやり方がわからないと思いますので、
次にその留意点を挙げます。

初学者の方は、そもそもやり方がわからないと思いますので、
次にその留意点を挙げます。
■ 「過去問」は、同じ問題を本試験までに少なくとも3~4回は解くものである。
但し、自分の中で完全に「この問題については理解できた」と実感したら、
もう解く必要はありません。代わりに他の同様の問題を解くべきです。
過去問はさかのぼれば、いくらでもあります。
■ 「過去問演習」の際には、ボールペンを使ってはいけない。
必ず鉛筆かシャープペンシルを使い、なるべく問題集そのものに
書き込みをしないようにしましょう。
なぜなら、先に申し上げた通り、過去問は同じ問題を複数回解くことが
通常なので、問題文上に痕跡を残してしまうと、次回以降、自らフラットに
学力をはかる際の妨げになるからです。
■ 世上、あまり言われていないことですが、
私は、 「過去問は古いものから解くべき」と考えます。
なぜなら、宅建試験の問題は、年々難易度が増しているからです。
従って、仮にあなたの目の前に、ある学習項目(例えば、民法の「代理」)の
令和5年、平成20年、平成15年の問題があるとしたら、
但し、自分の中で完全に「この問題については理解できた」と実感したら、
もう解く必要はありません。代わりに他の同様の問題を解くべきです。
過去問はさかのぼれば、いくらでもあります。
■ 「過去問演習」の際には、ボールペンを使ってはいけない。
必ず鉛筆かシャープペンシルを使い、なるべく問題集そのものに
書き込みをしないようにしましょう。
なぜなら、先に申し上げた通り、過去問は同じ問題を複数回解くことが
通常なので、問題文上に痕跡を残してしまうと、次回以降、自らフラットに
学力をはかる際の妨げになるからです。
■ 世上、あまり言われていないことですが、
私は、 「過去問は古いものから解くべき」と考えます。
なぜなら、宅建試験の問題は、年々難易度が増しているからです。
従って、仮にあなたの目の前に、ある学習項目(例えば、民法の「代理」)の
令和5年、平成20年、平成15年の問題があるとしたら、
平成15年⇒同20年⇒令和5年に並べ直して解くほうが、スムーズに理解でき、
脳に知識を納めやすいはずです。
■ 住宅新報出版の<分野別過去問題集>は解説も詳しく、すばらしい教材ですが、
掲載問題数が300問(⇒単純に考えて、本試験6ヶ年分)と少ないため、
学習に慣れてきたら、問題数が多く、解説が充実した
他の過去問題集を購入する必要があります。
購入するならば、予備校系(LEC・TAC・日建学院など)のものは、
解説も詳細で、バグも少ないのでおすすめです。
できれば、大きな書店で手に取って比較検討して下さい。
脳に知識を納めやすいはずです。
■ 住宅新報出版の<分野別過去問題集>は解説も詳しく、すばらしい教材ですが、
掲載問題数が300問(⇒単純に考えて、本試験6ヶ年分)と少ないため、
学習に慣れてきたら、問題数が多く、解説が充実した
他の過去問題集を購入する必要があります。
購入するならば、予備校系(LEC・TAC・日建学院など)のものは、
解説も詳細で、バグも少ないのでおすすめです。
できれば、大きな書店で手に取って比較検討して下さい。

2025年03月10日
必ず、「予習」をしよう!
現在、私たちが行っているのは、「法律」の学習です。
法律は、条文そのものが硬質ですから、その解説テキストもいきおい
硬い文章にならざるを得ません。
これを「初見で理解せよ」というほうが無理な話です。
そこで、授業に臨むにあたっては、
とりわけ初学者(=初めて「宅建」を学習する方)は、
テキストの下読み程度の「予習」をしてきたほうが、理解度が高まると思います。
「予習」の際には、
テキストの、(自分が理解しにくいところ)に、軽くしるしをつけておき、
私の講義がそこにさしかかったら、特に集中して聴く、
というやり方が効果的かと思います。
目安としては、2単元先くらいまで目を通しておけばいいでしょう。
授業は、1週間のうちのたった2時間しかありませんので、
そこからたくさんのものを家へ持ち帰り、
家庭学習でそれをふくらめたり、深掘りしたりするように心がけて、
日々 実力をつけていきましょう!

法律は、条文そのものが硬質ですから、その解説テキストもいきおい
硬い文章にならざるを得ません。
これを「初見で理解せよ」というほうが無理な話です。
そこで、授業に臨むにあたっては、
とりわけ初学者(=初めて「宅建」を学習する方)は、
テキストの下読み程度の「予習」をしてきたほうが、理解度が高まると思います。
「予習」の際には、
テキストの、(自分が理解しにくいところ)に、軽くしるしをつけておき、
私の講義がそこにさしかかったら、特に集中して聴く、
というやり方が効果的かと思います。
目安としては、2単元先くらいまで目を通しておけばいいでしょう。
授業は、1週間のうちのたった2時間しかありませんので、
そこからたくさんのものを家へ持ち帰り、
家庭学習でそれをふくらめたり、深掘りしたりするように心がけて、
日々 実力をつけていきましょう!

2025年03月04日
まず、森を見よ[民法の全体構造を把握しよう]
さて、皆さんとはまず、私法の一般法である民法から学習し始めますが、
民法は、1050条もの条文からなるボリュームのある法典で、
我々の生活にとって、とりわけ重要な法律です。
宅建試験の学習としての「民法」は、司法試験や司法書士試験のそれと異なり、
学習内容に若干の偏りがあるのですが
(宅建民法では、法人や占有権はほとんど取り扱わない)、
それでも多くのことがらを学んでいきます。
その際に気を付けなければならない視点が、

民法は、1050条もの条文からなるボリュームのある法典で、
我々の生活にとって、とりわけ重要な法律です。
宅建試験の学習としての「民法」は、司法試験や司法書士試験のそれと異なり、
学習内容に若干の偏りがあるのですが
(宅建民法では、法人や占有権はほとんど取り扱わない)、
それでも多くのことがらを学んでいきます。
その際に気を付けなければならない視点が、
「 まず、森を見よ! 」 ということです。
要するに、初めから1本1本の木をつぶさに見ていくのではなく、
森、すなわち”全体構造”を把握し、脳内にそのスペースを確保した上で、
その中に1本1本の木を収めていく(=内容を理解していく)という
学習の進め方のことです。
民法は、次の5つのかたまりから成り立っています。
第1編 総則
第2編 物権
第3編 債権
第4編 親族
第5編 相続
そして、一般的に、1・2・3編を「財産法」、4・5編を「身分法」と呼び、
同じ民法典の中にありながら、両者は性格を異にしています。
ここからの詳細は、授業の中でお話ししますが、今後の法律学習では、
まず、この全体構造を把握するクセをつけていって下さい。
要するに、初めから1本1本の木をつぶさに見ていくのではなく、
森、すなわち”全体構造”を把握し、脳内にそのスペースを確保した上で、
その中に1本1本の木を収めていく(=内容を理解していく)という
学習の進め方のことです。
民法は、次の5つのかたまりから成り立っています。
第1編 総則
第2編 物権
第3編 債権
第4編 親族
第5編 相続
そして、一般的に、1・2・3編を「財産法」、4・5編を「身分法」と呼び、
同じ民法典の中にありながら、両者は性格を異にしています。
ここからの詳細は、授業の中でお話ししますが、今後の法律学習では、
まず、この全体構造を把握するクセをつけていって下さい。

2025年02月28日
「体系的理解」の重要性~YouTube学習の危うさについて~
私の講座では、各法律の詳細な説明に入る前に、
その法律の「全体構造」についてお話しすることにしています。
とりわけ民法は、相当ボリュームのある法典なので、
「まず、森を見る」ことから始めないと、道に迷ってしまいます。
昨今、YouTubeにアップされている動画で、
「宅建」を学習する方も増えているようですが、
ご自宅で自分の好きな時間に学習できるメリットがある反面、
ひとつ懸念すべきことがあります。
それは、YouTube 学習は、「論点ぶつ切り」的な学習であるがゆえに、
体系的理解をおろそかにしがちだ、ということです。
「宅建」の授業がYouTubeにアップされている理由は、
その講師が、自らのスクールに生徒を勧誘するために、
全体講義のうちの一部、あるいは
YouTubeのために特別に撮影した動画を見せているものと思われ※、
当然、30回、40回というシリーズでアップされてはいません。
※その講師のファンがアップする場合もあるでしょうが、
それも著作権的、ビジネス的に好ましくありません。
したがって、論点や項目ごとの理解はできても、
それらのタテ・ヨコのつながりや、
私がよく言う、<民法と宅建業法の有機的なつながり>
などについては軽視されがちです。
頭の中に、法律を体系的におさめこんでいくことで、
いざという時に、知識をすぐに引き出すことができます。
そのような意味で、私は、YouTube学習は、
「ひと通り、体系的理解が済んだ後で、復習的に使うのが適切である」
と考えます。
さあ、もうすぐ開講です。
私と一緒に、法律の「体系的理解」を心がけて、
今年、必ず「合格」しましょう!

その法律の「全体構造」についてお話しすることにしています。
とりわけ民法は、相当ボリュームのある法典なので、
「まず、森を見る」ことから始めないと、道に迷ってしまいます。
昨今、YouTubeにアップされている動画で、
「宅建」を学習する方も増えているようですが、
ご自宅で自分の好きな時間に学習できるメリットがある反面、
ひとつ懸念すべきことがあります。
それは、YouTube 学習は、「論点ぶつ切り」的な学習であるがゆえに、
体系的理解をおろそかにしがちだ、ということです。
「宅建」の授業がYouTubeにアップされている理由は、
その講師が、自らのスクールに生徒を勧誘するために、
全体講義のうちの一部、あるいは
YouTubeのために特別に撮影した動画を見せているものと思われ※、
当然、30回、40回というシリーズでアップされてはいません。
※その講師のファンがアップする場合もあるでしょうが、
それも著作権的、ビジネス的に好ましくありません。
したがって、論点や項目ごとの理解はできても、
それらのタテ・ヨコのつながりや、
私がよく言う、<民法と宅建業法の有機的なつながり>
などについては軽視されがちです。
頭の中に、法律を体系的におさめこんでいくことで、
いざという時に、知識をすぐに引き出すことができます。
そのような意味で、私は、YouTube学習は、
「ひと通り、体系的理解が済んだ後で、復習的に使うのが適切である」
と考えます。
さあ、もうすぐ開講です。
私と一緒に、法律の「体系的理解」を心がけて、
今年、必ず「合格」しましょう!