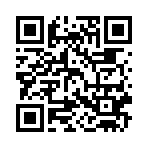2021年12月31日
合格体験記 5 (下)
M.D さん(イーラde沼津校 50歳代 男性)
(中から続く)
権利関係の過去問を解いていて思ったこと
権利関係は、たくさん勉強してもなかなか点に結びつかない
そうです。自分も訳がわからない長文問題が多いと感じて
いましたが、それでもだいたい6割、7割くらいは正解していました。
基本的な事項は理解していたつもりですが、文章を根気よく
読むことが正解につながると思います。
間接的ですが、自分は毎日、新聞やヤフーの長文記事を
最低30分以上読んでいたのでその習慣が役に立ったのでは
と思っています。
宅建業法の過去問を解いていて思ったこと
宅建業法は過去問を完璧に習得すると試験で満点を目指せる
科目です。
ただし、自信過剰になっているひっかけ問題でつまずくことがあります。
試験の文章には独特のくせがあります。
文章中に「必ず」「直ちに」「常に」「すべて」「〇〇に限って」「有無に
かかわらず」という単語が出てくると誤りに、反対に「〇〇のことがある。」
「〇〇の場合がある。」と言うときは正しいとなることが多いようです。
また「〇〇なので××である」という文章は前後の内容で正しいと誤りが
混在していることが多いようです。あくまでも可能性なので、
問題ごとに注意する必要があります。
試験の際に行っていたこと
正しい番号を選択する場合と誤りの番号を選択する場合の2種類の
問題があり、たまに勘違いして解答してしまうことがあります。
そのため問題文の選択する内容について必ず丸で囲んでいました。
また長文の問題は短い文節で区切るように斜線を入れていました。
全体を通して、最初の解答の際は、簡単な問題、難しい問題、
迷っている問題を分類し、〇×△と問題番号に印をし、とりあえず
解答をマークして、2回目、3回目と見直しを行いました。
多分できたと思った問題については一応見返しましたが、
主にマークミスがないかの確認にとどめました。
勉強以外に行っていたこと
自分は毎回の講座の前に、ガイダンスの際に先生から頂いた
得点バランス分析表を眺めていましたが、本試験の結果は、
目標点がすべての科目で一致していました。
また、おまじないとして、自宅の壁の毎日必ず目にする場所、
数ヵ所にA4の紙にマジックで「宅建試験合格しました。
ありがとうございました。」と書いて貼っていました。
宅建士合格講座の感想
沼津校の講座生の皆さんは、ほとんど休みなく、講座開始
10分前には全員揃っていました。チェックシートも多くの方が
毎回提出しており、未提出の自分は少し肩身の狭い思いを
していました。私は講座では、一番後ろの席でしたので、
家で学習をしているときも、試験のときも、後ろから、
いつも見ていた皆さんが一生懸命勉強している姿を
思い浮かべて、気持ちを高めていました。
また、先生の話していた場面を思い出しては、重要ポイント
について、記憶の定着に役立てたりしていました。
独学だとこんな経験は絶対できないので、もし受講していなかったら
試験に合格していなかったかもしれません。
改めまして先生や講座の皆さんに心より感謝を申し上げます。
==========================
(講師より)
Dさんがおっしゃるように、「権利関係」での難問・奇問の出題は
悩ましい問題です。
しかし、難問・奇問は、ほとんどの受験生にとって難問・奇問なので、
そこは気にせず、「基本的事項や頻出事項を確実に得点する」
ことに精力を傾けていただきたいです。
合格発表日まで自己採点しなかった方が、合格していたという
ケースは、私の経験上初めてでしたので、たいへん驚きましたが、
何はともあれ、合格おめでとうございました!

2021年12月30日
合格体験記 5 (中)
M.D さん(イーラde沼津校 50歳代 男性)
(上から続く)
本試験を受けての感想
解答する順番は、宅建業法、その他、法令上の制限、税法、
権利関係で、全体で1時間半くらいで解答は終了しました。
問題のうち、過去問でもテキストでも見たことがないような
難問奇問が権利関係と法令上の制限、税法で合計5問ほど
出題されましたが、そのうち1問しか解答できませんでした。
連れ子の相続権とか美術品とか宅建どう関係があるのでしょうか。
合格点を下げるための問題としか思えないため、試験に対して
非常に否定的な印象を持ちました。
おまけに宅建業法とその他の問題では解答の選択に迷うものが
複数ありました。
このため、合格点に到達するほど正解できたとはとても
思えませんでした。
合格発表
試験後は、難問奇問の衝撃が強烈で、全体的に難しかったと
いう印象があり、感覚的には31点ぐらいと思ったために、
勝手に不合格と判断し、自己採点もしませんでした。
合格発表の当日は、一応確認だけはしておこうとパソコンを
見ていましたが、番号を見つけたときは、たいへん驚いて、
番号を何度も見返しました。
この時に初めて自己採点したところ、実は38点であることが
判明しましたが、実際に合格証書が届くまでは、半信半疑
でした。
使用テキスト
講座で使用した基本書。同シリーズの要点整理と一問一答。
それ以外に使用する市販の参考書はカラーで見やすく、
わかりやすいもの、持ち運びが楽な本をおすすめします。
できれば同じ出版社に統一し、過去問題集は必ず買って下さい。
時間に余裕があれば直前予想問題集も有効だと思います。
古本屋でも購入できますが、法の改正があるため、
できるだけ年度が新しものにして下さい。
勉強時間
自分は講座を含めても200~300時間くらいでしょうか。
全体的には少な目ですが、試験直前の2ヵ月くらいは、
ほぼほぼ毎日平均4~5時間は勉強していたと思います。
暗記の要素が大きな試験なので、短期間にいかにたくさんの
問題を解くかで合格に近づくと思います。
そのため、試験直前にできるだけ勉強時間が多く取れるような
計画を立ててください。
やるべきことをやって過去問50問中で平均35点くらい
とれるくらいのレベルに到達したらかなりの合格の可能性は
高くなっていると思います。
YouTube について
YouTubeでは宅建に関するチャンネルが多く存在します。
私は特に毎日10分程度配信される〇〇大学という
2つのチャンネルをよく視聴していました。
毎日数千回以上再生されているので、結構人気があると
思います。2人とも早口で熱く語る人達なので、自分は
知識を養うというより気持ちを高めるため、夜寝る前に
拝見していました。
宅建の勉強をしていると気持ちが落ち込む場面や不安に
なる瞬間が何度もありましたので、そういう時の栄養剤の
役目を果たしていたと思います。
(続く)

2021年12月29日
合格体験記 5 (上)
宅建士試験合格体験記

M.D さん(イーラde沼津校 50歳代 男性)
私は今年初めて宅建試験を受験しましたが、
おかげさまで合格することができました。
そこで、誠に僭越ではございますが、今年どのように
勉強していたのかをお伝えいたします。
3月~7月上旬まで
SBS学苑の講座開講から勉強を開始しましたが、週1回、
講座開始前30分くらいの時間でテキストの予習、講座終了後、
自宅で夜寝る前に30分くらい復習という形で7月くらいまで続け、
チェックシートも作成していませんでした。
かなりのんびりしていましたが、性格的なものと、5月中旬に
身内に不幸があり、精神的に動揺していたことが原因だと思います。
7月中旬~9月上旬まで
7月の試験申し込みの際に、やっと本格的に勉強を始める決心を
して、市販の科目別問題集を購入し問題を解き始めました。
その際には、専用のノートを作り、〇×をどの問題の、
その番号に付けたかを後から見てもわかるように整理しました。
最初は中々正解できなかったのですが、同じことを3回繰り返し、
3回目終了後に市販のテキストを購入し通読しました。
9月中旬~9月下旬まで
引き続き分野別問題の演習とテキストの確認を行い、同時期に
専門学校の模試を3回受けましたが、この時点でもまだ試験問題は
難しく感じられました。試験結果は平均30点未満でC判定となり、
本試験はたぶん合格しないだろうと思いました。
10月上旬~本試験まで
市販の過去12年分の試験問題集を購入し、問題を解き始めました。
それと同時に科目別問題集で3回解答して不正解だった問題に
付箋を貼り何度も見返しました。問題集と並行してテキストにも
付箋を貼り、特に法令上の制限や数字に関連する部分の暗記を
繰り返し、権利関係と宅建業法などの他の科目についても
忘れないように基本的事項を見返しました。
この頃、講座の模試を受け、最初の2回の平均は35点でしたが、
3回目は21点でした。
12年分の試験問題集が終了してからは、さらに、市販の直前予想
問題集を購入し、問題を解き始めましたが、ほぼほぼ合格点が
取れるようになりました。
試験当日
1時間前には会場につき、5問免除問題と数字に関連する
暗記項目を確認しました。
30分前にはトイレを済ませましたが、受験者は沼津会場で
1000人くらい集まっていた感じで、トイレに行列ができていました。
持ち物は、薄い上着と、消しゴム3個、シャープペン2本、
鉛筆1本を用意しました。
(続く)

2021年12月28日
合格体験記 4 (後編)
T.I さん(パルシェ校 20歳代 女性)
(前編から続く)
個人的には、私は書くことが好きではないので、
ノートを使用しないことにこだわりました。
授業中にメモを取る際はただの紙、問題を解く際は裏紙に書いて
すぐに捨てる等、丁寧に書こうという意識がなくなることで、
勉強が苦しくなくなりました。
まとめ作業もほとんどせず、「要点整理テキスト」を活用しました。
初めは読むことも好きではないので、「基本書」があればいいと
思っていました。しかし、学習が進むにつれて前にやったことを
忘れてしまい、見慣れたはずの「基本書」もどこに何が書かれているか
分からなくなってしまいました。
そのようなときに「要点整理テキスト」を見ることで、
簡単に思い出すことができ、
その後はすぐに対象ページを開けるようになるまで、使いこみました。
通勤時間は、「合格体験記」を中心に先生のブログを読みこみました。
合格者の方には及ばず、私は247時間ほどでしたが、
自分の学習時間や解いた問題数を合格者の方と比較することで、
まだまだやらないと受からない、そんな気持ちになりました。
直前期は、記録表を参考に、過去に間違えた問題を中心に
解き直しをしました。
正解しても不安なところは「要点整理テキスト」を見返し、
印をつけるようにしました。
講座では演習ⅠⅡ、模試と3回試験と同じ雰囲気で50問解くことができ、
外で模試を受けなかった私にとってはとてもありがたかったです。
試験というもの自体久しぶりで、1回だけでは不安が残っていたように
思います。
試験は、会場前での体温測定を通過すると、
無事に試験が受けられると思いほっとしました。
緊張はしましたが、オリンピック選手のように
楽しむことを意識しました。笑
手応えはありませんでしたが、自己採点は39点。
もっと先生に質問していたらという思いや、
あの1週間勉強していなかったという後悔、
試験後も不安は続きましたが、今は合格できて嬉しいです。
途中からではありましたが、先生の講座と出会えて、
本当に良かったです。
「合格して可能性を広げる」
ふわっとした目標を立てて始めた勉強でしたが、
先生の授業を受けて行くうちに、憧れも、合格したいという思いも
強くなりました。
結果を出せる1年を過ごせたのは久々です、
次につなげていきたいと思っています。
本当にありがとうございました。
==========================
(講師より)
「合格体験記」を読み込んで、過去の合格者のやり方を参考にした、
という箇所に、I さんの戦略性を感じました。
「要点整理テキスト」を活用する方とそうでない方が
いらっしゃいますが、I さんは前者ということで、
できれば私も、受講生の皆さんにその方向で
推奨したいと思っています。
せっかく取得したライセンスですから、活用できるといいですね。
本当に、おめでとうございました!

2021年12月27日
合格体験記 4 (前編)
合格体験記

T.I さん(パルシェ校 20歳代 女性)
今年の宅建試験、私にとっては2018年以来2度目の挑戦でした。
前回は7月から独学で勉強を始め、33点。
あと4点で合格、もう少し早く勉強を始めれば次は大丈夫と
思っていましたが、あと少しになってから点数を上げるのが
難しいと分かった今は、講座に通って本当に良かったと思っています。
先生より「前回の分析から始める」という話があり、
前回はどの分野で何点を取っていたのかをまず確認しました。
権利関係と業法であと5点必要と分かり、より一層気合いが入り
勉強をスタートさせました。
また、2回目以降の人は「一問一答がおすすめ」とのことで、
講座を受けはじめてすぐに購入しました。
授業中は、B5の用紙に、テキストのページ数と先生の話を
ひたすらメモしました。
先生の授業は小テストや指名されて答えるといったことがなく、
最初は眠くなってしまうのではないかと思いましたが、
仕事で全く復習出来ていない週であっても安心して講座に
行くことができたので良かったです。
授業の次の日は、テキストを読みながら対象のメモを書き込み復習。
授業で学習した範囲の「一問一答」を解き、過去問集を2冊分解きました。
「一問一答」で間違えて覚えることで、過去問集では四肢の中から
正解を選ぶことができる。
身についている実感があり、楽しく勉強できました。
過去問集は9月末までに2092問解き、先生からいただいたチェックシートに
記録。授業のたびに提出し確認いただけるので、
自分一人で取り組むのとは全く意識が違いました。
どの分野のどの問題を間違えているか、正解しているか、
いつから解いていないか、問題集を開かなくてもすぐに分かるように、
記録表を作成しました。
1周目、2周目と正解率を出し、解けるようになっている実感を
持てるようにしました。
過去問は、学習が済んだ分野ごとに解き、
先生に示して頂いた目標点に達しているか確認しました。
10年分解きましたが、そのうち6年分は50問まとめて解くようにしました。
購入した模試は2回分、10月に入ってから使用しました。
(続く)

2021年12月26日
合格体験記 3 (下)
K.T さん(イーラde沼津校 20歳代 男性)
(中から続く)
[試験当日~試験中]
試験当日は早めに会場入りし、出題頻度の高い分野に絞って
全体の復習を行いました。
模試の時に、直前勉強に没頭しすぎてお手洗いに行きそこない
後悔したことがあったので、忘れないようにお手洗いを済ませました。
試験が開始し、26問目から解き始めました。
私は宅建業法が一番得点率が高かったので、26問目からにしていますが、
人によって解きやすい順番があるかと思います。
実際後半の問題で点数を取れたという安心感があったので、
前半に難しい問題が来ても焦らず進めることができました。
ただそれでも時間がぎりぎりで、見直しする時間は取れませんでした。
模試では見直しが終わっても時間が余っていたのですが、
本番では緊張からか時間配分がうまくいってなかったみたいです。
[講座を受け終えて]
週一で講義に参加することにより、勉強のペースを作ることができた
というのが大きかったと思います。
また、周りに一緒のゴールを目指して頑張っている人がいると実感でき、
勉強する励みになりました。
どうしても日程が合わなかったときに、DVDやYouTube で
補講が受けられる制度は助かりました。
来年度からはYouTube 講座も始まるようですが、対面で講義を受けた後、
気軽にYouTube で復習できる制度があれば、受講生からすると
一層ありがたいのかなと思いました。
(システム的に難しいのかも知れませんが)
[終わりに]
宅建試験は難しく、年1回しか受けられないので、
落ちた時の絶望感はかなり大きかったです。
逆に合格した時の達成感や開放感もかなり大きく、
柄にもなく声を上げて喜びました。
これから宅建試験に挑戦される方にも同じ喜びを是非味わって
いただきたいです。
つたない文章で申し訳ないのですが、少しでも参考に
なりましたら幸いです。
ご覧いただきましてありがとうございました。
========================
(講師より)
以前、この講座で合格された受講生様からのご紹介で入学された、
寡黙な男性です。
クールな印象の彼だけに、
「柄にもなく声を上げて喜んだ」のくだりから、
合格の喜びの大きさが一層伝わってきました。
確かに、「宅建合格」は、それほどのインパクトがあります。
なにせ、その方の一生を左右してしまうほど大きな
ライセンスなのですから。
後に続く皆さんも、ぜひその喜びを味わいましょう!
あらためまして、合格おめでとうございました!

2021年12月25日
合格体験記 3 (中)
イーラde沼津校 合格者のDさん!
恐れ入りますが、私までご連絡下さい!(054-653-0535)
「合格体験記」もお願いします!
久保
==========================
K.T さん(イーラde沼津校 20歳代 男性)
(上から続く)
・8月~9月
8月に入り、一度 市販の本の模擬試験を家で
試験形式で行いました。
結果時間が足りず、点数も散々で「これはやばい!」と
思い始めました。
勉強方法としては、過去問10年分を解くことと復習、
「要点整理テキスト」を読み込むことを中心に進めました。
過去問は12年分を解いたほうがいいとは思いましたが、
勉強する時間が足りなかったので、10年分に絞り
復習することに時間を充てました。
・10月
模試は外部模試も含め2回受けました。
模試は自分が苦手な部分も分かること、
時間配分や問題を解く順番を試すことができること、
本試験の予想問題のデータを集めることができることの
メリットもあるので、複数受ける方がいいと思います。
試験直前は自分の苦手箇所を中心に、
過去問復習と「要点整理テキスト」の読み込みを行いました。
また宅建の試験はどんなに難しい問題でも25%で
当たる可能性があるため、少しでも運を上げようと
合格祈願のお参りを行いました。
・全体を通じて
どうしても覚えられなかったり、苦手な分野は捨てるという
選択肢もありだとは思います。
私の場合、用途制限と難しい計算問題については捨てました。
ただ、簡単な問題が出たときは解けるくらいには勉強時間を
充てました。
また、不動産業界にお勧めの方限定になってしまいますが、
5問免除は必ず受けたほうがいいと思います。
お金もかかりますが、100% 5点が取れる安心感と、
その部分を一切勉強しなくていいというメリットは大きかったと
感じました。
(続く)

2021年12月24日
合格体験記 3(上)
合格体験記
K.T さん(イーラde沼津校 20歳代 男性)
久保先生、この度は大変お世話になりました。
おかげ様で無事に合格する事が出来ました。
感謝申し上げます。
微力ながら私なりの合格体験記を書かせていただきます。
[結果]
自己採点38点(5問免除含)
本格的に勉強を始めて2回目の受験
去年は独学で自己採点30点
[職業]
不動産営業 2年目
[受講のきっかけ、理由]
・去年は独学で進めて勉強のペースをうまく掴めなかったため。
・奨学金の返金分を考えるとお得だと思ったため。
上司からの紹介もあり、受講を決めました。
[勉強方法]
一度通しで勉強していたので、大まかな概要については
頭に入っている状態からのスタートでした。
ちなみに去年の一番最初は宅建の漫画を読むことと
YouTube の動画を聞き流すことから始めました。
また、知識がほとんどない状態で一度1年分の
過去問に目を通しました。
・3~7月
長期的に集中して勉強するのが苦手なので、
前もって7月くらいまでは緩く勉強すると決めていました。
ただ振り返ってみると、終盤勉強時間が足りないと感じたので、
もう少し早くからスイッチを入れればよかったと思いました。
勉強方法としては、授業の復習、要点整理テキストを読み込み、
一問一答を中心に進めました。
(続く)

2021年12月23日
合格体験記 2 (下)
Y.T さん(パルシェ校 40歳代 女性)
(中から続く)
[メンタルについて]
モチベーションを維持するのがとても大変でした。
何度も挫折しそうになり、そんな時は自分にご褒美買い物などをしました。
また、長時間の勉強が苦手だったので、週末はなるべく1時間おきくらいに
休憩を入れて実施、平日は時間があるときは長くても2時間まで、
休憩をはさみ、集中力アップするようにしました。
[だいたいの勉強時間数]
5月までは仕事をしながらだったので、仕事が休みの日は2時間ほど実施。
6月以降は、家事・学校などの用事が済んでから午後から2時間ほど、
子供が寝てから30分~1時間ほど、計3時間ほど実施。
9月以降の週末は、5~8時間実施。
[振り返ってみて]
予習・復習が基本の力となる。
問題をいかにたくさん解くか、文章に慣れることが大事。
プラスアルファで、外部模試や書店で模擬テストを購入し実施すると、
本番のイメージがしやすい。
バランスよく点を取らなければならないため、捨てる分野はない。
これから宅建士を目指す方、初めて「宅建」というものに臨んだ私でも、
最後までやり抜けました!やればできます!
自分を信じて頑張って下さい。
読んでいただき、ありがとうございました。
=============================
(講師より)
本年度の3校の中で、最も「チェックシート」を提出された方です。
宅建業と関係のない初学者の方で、”一発合格”ですから、
その学習方法には、見習うべきところが多いと思います。
「宅建」は確かに難関試験ではありますが、
こうして実際にこの講座から”一発合格”されているわけですから、
後に続く皆さんに、大きな励ましになることと思います。
本当に、おめでとうございました!

2021年12月22日
合格体験記 2 (中)
Y.T さん(パルシェ校 40歳代 女性)

(上から続く)
・9月:「過去問12年間」を、3回目は業法の25問あたりから始めて、
時間を区切って実施。
→25問~50問で50分/1問~24問で1時間10分
※ 途中から権利関係はやめ、業法他に集中。
その代わり「分野別問題集」で確認。
「直前予想模試(3回分)」を購入し、自宅で本番同様、
時間を計り実施。
※ 学苑での答案練習(2回)+直前模試→必ずその週中に解説理解、
間違えた箇所を解く。
・外部模試 9月1回:必ずその週中に解説理解、間違えた箇所を解く。
・10月~試験直前:「過去問12年間」「直前予想模試(3回分)」を、
再度実施(4回目)し、少しでも選択に悩んだらチェック、
チェックした問題を実施。
※ 時間の許す限り実施、苦手な分野を集中的に何回もやる。
権利関係を「基本書」または「要点整理」にて復習
→過去問を見て出やすい分野を実施。
[必ず行ったこと、気を付けたこと]
①出来る限り予習・復習をし、復習はその週のうちにしました。
→予習ができないときは、「要点整理」を見て、流れをつかむ。
まとまった時間が取れなかったため、空いた時間に
とにかく問題を解くようにしました。
②模試を受けたり、問題を解くうちに、自分が苦手な分野や言い回しが
分かってきたので、とにかく問題をやって文章に慣れ、
苦手な箇所を集中して解くようにしました。
(ex. 権利関係を解くときは、必ず関係図を記すなど)
③毎月の目標を必ず立て、先生が「やったほうがいい」ということは、
出来る限りやるようにしました。
④業法は、問題内容が豊富で、業法だけでは自分は得点できなく、
法令上の制限や税その他は業法ほど広くはなかったので、
法令上と税にも力を入れました。
最初に13問目~50問を50分で、次に1問~12問を残り時間で
解けるようにしました。
→権利関係は問題文が難しく、読解するのに時間がかかるため、
先に暗記である程度クリアできる業法とその他を1時間以内で
解くことで、焦らず権利関係に取り組むためです。
(続く)