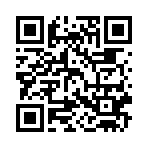2016年04月28日
「宅建 実力養成講座」のご案内
本年度も、SBS学苑 パルシェ校にて「宅建 実力養成講座」を開講致します。
この講座は、(要点整理テキスト)を用いて行う、
宅建試験の「重要論点」「頻出事項」の短期集中型講座です。
もともとは、中・上級者向けに企画した講座ですが、初学者の方でもかまいません!
さあ、あなたも、今年の合格に向けて参加しませんか!
[開講日]
パルシェ校のみ :平成28年6月27日(月)19:00~21:00 全12回
※ 最終回:10月2日(日)13:00~16:00 直前予想模擬試験
〈 無料ガイダンス 〉 6月13日(月) 19:00~20:00
http://www.sbsgakuen.com/gak0020.asp?gakuno=2
※詳しくは、学苑事務局(054-253-1221)までお問い合わせ下さい。

2016年04月27日
第8回目の講義のポイント
「担保物権一般・質権」の学習です。
債権がひと区切りし、いよいよ物権の本格的な学習に入りました。
将来の実務を見据えながら、楽しく学習できる工夫をしていきましょう。
「連帯債務」
①意義、保証・連帯保証との違い
②「絶対的効力事由」の理解と、6項目の暗記
時間とのかねあいもあり、授業では、P90、91をつぶさに読みませんでしたが、
自分で必ず読んで、理解しておくこと
「用益物権」
①意義、所有権との違い
②地上権の意義、(土地の)賃借権・借地権との関係性の理解
③地役権の意義
「相隣関係」 授業で読んだ部分の理解
「担保物権一般」
①担保物権の意義、「留置的効力」と「優先弁済的効力」の理解、
4種類の担保物権の分類
②担保物権の性質(附従性・随伴性・不可分性)⇒物上代位性は次回
「質権」「留置権」「先取特権」
①意義、物上保証(人)の意義
②授業で話した具体例を想起できるようにしておくこと
さて、いよいよGWが始まりますが、お休み期間中に少しでも、
ここまで学習してきたことの復習をしておくことをおすすめします。
皆さんは今年、受験生ですので、その自覚を持って時間を有効に使って下さい。

2016年04月25日
「熊本地震」義援金についてのご報告
受講生の皆さんからお預かりした表記 義援金が
静岡新聞にて確かに受け付けられた旨の記事が掲載されましたので、
ここにご報告申し上げます。
ご協力ありがとうございました。
被災地の一日も早い復興と、被災者の皆さんが早期に平生の生活を
取り戻されますことを強く願っております。
2016年04月22日
「熊本地震」義援金 払込み完了のご報告
1週間前の先週の木曜日に、熊本で震度7の地震があり、
その後 隣接する大分などでも関連した地震が続きました。
現地の惨状、被災された皆さんの日々の生活の困難さは報道の通りです。
さて、本年度「宅建士合格講座」受講生の皆さんから、
標記地震に係る被災者支援のための募金の趣旨についてご賛同いただき、
昨日の沼津校で、3校分の募金がまとまりましたので、
本日(4月22日)、郵便局にて義援金の払い込み手続きをして参りました。
ご協力いただいた皆さんに厚く御礼申し上げますとともに、
謹んでここにご報告申し上げます。
※金額は、募金後の事務処理のことを考え、調整させていただきました。
被災地が一日も早く復興し、被災者の皆さんが早期に通常の生活に戻れますよう
願っております。
我われは、「 いま、勉強できることのありがたさ 」を、チカラに変えて、
本試験「合格」に向けて、邁進して参りましょう。
2016年04月18日
第7回目の講義のポイント
「その他の債権消滅原因」「保証債務」です。
この中ではとりわけ、「保証債務」(10か年中5回の出題頻度)が重要です。
「債権譲渡」
①指名債権譲渡の債務者に対する対抗要件
⇒民法467条1項の理解
② 同 第三者に対する対抗要件
⇒債権の二重譲渡の場合の判例の理解
「弁済・相殺」
各々の意義と、過去問のマーキングが出ている箇所の理解
「その他の債権消滅原因」
各制度(法律用語)の意義
※次回学習する「連帯債務」で必要となる
「保証債務」
①保証契約の当事者
②民法446条2項の趣旨
③保証債務の性質
④連帯保証の特質
皆さんもだんだんと「法律の学習」に慣れてきたはずです、
色んなパターンの過去問を解いて、本試験で、
”どこからどう問われても対応できる力” を身につけておきましょう!

2016年04月17日
「熊本地震」義援金について 2
4月15日(金)夜に、浜松市のSBS学苑 遠鉄校で授業がありました。
私がその日の午前中に書いたブログを
すでにご覧いただいていた受講生の方もいらして、
お教室に入ってすぐに、私の手作り「募金箱」に募金をして下さいました。
遠鉄校の受講生の皆さんの、温かなお気持ちを、
必ず、静岡新聞社に届けます。
(本日、静岡新聞社から 義援金についての発表がありました ↓ )
http://www.at-s.com/pressrelease/article/detail/231217.html
受講生の皆さんの中には、静岡新聞以外の新聞を購読されている方や、
すでにどちらかで募金をされた方もいらっしゃると思いますが、
SBS学苑の母体が静岡新聞社であるため、
今回の募金の窓口を静岡新聞社とさせていただいた次第です。
よろしくご理解のほどお願い申し上げます。
2016年04月15日
「熊本地震」義援金について
車で静岡市の自宅まで戻る途中のコンビニの駐車場でスマホを見ましたら、
Yahooのトップニュースに「熊本で震度7」という見出しがありました。
その後 帰宅して、食事をしながら、TV各局の報道にくぎ付けになりました。
あの「東日本大震災」から5年、
我々はともすると「のど元過ぎれば・・・」で、
地震の恐ろしさや日々の備えを忘れがちです。
また、「東海大地震」の危険性が叫ばれ始めて40余年、
我々、静岡県民こそが、まさにこれを機に、
一層 気を引き締めなければならないと思います。
さて、このブログを書いている10:00現在、
静岡新聞社のサイト上で発表はないのですが、
おそらく静岡新聞社は「熊本地震 義援金」の受付をはじめるものと思います。
そこで、5年前の「東日本大震災」直後にも実施したのですが、
今回も私が音頭を取り、
「SBS学苑 『宅建士合格講座』受講生 有志」名義で、
静岡新聞社へ義援金を届けたいと思います。
本日夜の遠鉄校⇒火曜日:パルシェ校⇒木曜日:沼津校 と募金を募り、
まとまった時点で、私が静岡新聞社本社へ義援金を届けたいと思いますので、
よろしくご協力のほどお願い申し上げます。

地震前の熊本城

2016年04月13日
任意代理と委任契約の相違点
委任契約とは、他人に契約などの法律行為をしてもらうことを委託する契約(民法643条)です。
委託する人を「委任者」、委託される人を「受任者」と言います。
ところで、このように、他人に法律行為を代わってやってもらうものとして、
皆さんとは既に「任意代理」を学習済みですね。
そこで、
「委任」と「代理」はどう違い、両者はどのような関係にあるのかを整理してみます。
まず、「代理」はA・B・Cの三者間の関係を規律するものです(テキストP20図 参照)。
つまり、代理人Bが本人Aのためにすることを示して、代理権の範囲内で、
相手方Cとの間で代理行為をなし、その法律効果が直接AC間に及びます。
これに対し、「委任」は、AB間の関係だけを規律するものであり、
受任者Bが委任者Aのために法律行為をする義務を、Aに対して負うというだけです。
受任者の相手方が委任者Aとどのような関係になるのかということは、
委任契約の射程範囲内には当然には入っていないのです。
従って、 「委任」と「代理」は異なるもの であり、受任者が必ずしも代理人になるわけではなく
(受任者が代理人になるには、委任契約とは別に、代理権授与が必要であるというのが多数説)、
また、事務処理も必ずしも委任者の名を示してするわけではありません。
しかし、両者が極めて深い関係にあるのは事実であり、法律行為を委任する場合には、
事務処理の便宜上、代理権を授与するのが一般的です。
従って、委任者が代理でいう「本人」、受任者が「代理人」になることが実務上は多いと言えます。
以上ですが、本試験対策上は、その出題が「代理」の知識を問うているのか、
「委任契約」の知識を問うているのかは、一見してわかりますので、
本試験対策として、過度に神経を使う必要はありません。

2016年04月11日
第6回目の講義のポイント
第6回目(権利関係5)は、「債務不履行」「契約の解除」「危険負担」
「債権者代位権」です。全般的に、出題頻度は高くないものの、
とりわけ前二者は、実務的には重要ですから、
私が授業で読んだ以外の部分にも、必要に応じて目を通しておいて下さい。
「債務不履行」
①三類型の意義と効果
②「損害賠償額の予定」の趣旨と、「違約金」との関連性
「契約の解除」
①「取消し」との違いを説明できるようにすること
②P66(4) 三段落目の理解(P15 判例との比較)
「危険負担」
本当は、じっくりと時間をかけて理解したい論点なのですが、
いかんせん出題頻度が低いので、概略の説明にとどめます。
①意義、「債権者主義」と「債務主義」の意義
②特定物売買における民法の原則と、実務の取り扱い
「債権者代位権」
①意義と要件
②平成22年出題 過去問の演習をしておくこと

2016年04月04日
第5回目の講義のポイント
「贈与・請負・委任」ほかの学習です。
とりわけ「売主の担保責任」は、頻出事項ですから、
この制度を自分で本当に納得できるまで、学習しておきましょう。
「条件と期限」
停止条件と解除条件が、実際にどのような局面で使われるのかを理解すること
(私がボードに書いたモデル図を自分で表現できること)。
「他人物売買」
一見、荒唐無稽な話のように聞こえますが、
この条文が果たしている役割と、法律効果について理解すること
「売主の担保責任」
<権利の瑕疵~>と<物の瑕疵~>の要件と効果、
最終的には、P45 表中の、意識的に覚えるべき点を確実に覚えること
「贈与・請負・委任」
各契約の定義と、私が授業の中で事例を挙げ、時間を割いて説明した点につき、
理解しておくこと
5回目が終わったということは、カリキュラム全体の6分の1が終わったということです。
全体の中では、今がいちばん、理屈の多い勉強です。
民法が終われば、少し楽になりますので、あともう少し、がんばりましょう!
 SBS学苑「宅建合格講座」は、今からでも入学できます。
SBS学苑「宅建合格講座」は、今からでも入学できます。詳しくは、もよりの学苑事務局までお問い合わせ下さい。
http://www.sbsgakuen.com/