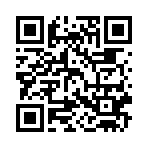2019年05月28日
(第11回) 講義のポイント
第11回目(権利関係10)は、「不法行為」と「共有・区分所有権(の一部)」でした。
「一般的不法行為」
そもそも「不法行為」は、(契約に基づかない債権・債務関係)というカテゴリです。
学習するボリュームが少ない割に、出題頻度も高く、
社会生活上も必要な知識ですので、しっかりと自分のものにしましょう。
①意義と、成立要件(できれば、意義から導き出せるようにしておくこと)
②効果(とりわけ、損害賠償請求権の消滅時効)
「特殊的不法行為」
①「使用者責任」の成立要件と効果
②「土地工作物責任」の成立要件と効果
「共有」
①保存行為・管理行為・処分や変更のための要件
②共有持分の譲渡・放棄、共有物の分割
「区分所有権」
区分所有法は、すなわち”分譲マンション法”です。
毎年1問出題されますし、実務で取り扱う機会も多いので、
分譲マンションにお住まいでない方も、
この機会に、その権利関係の特殊性について、理解を深めておきましょう。
⇒項目が細かいので、私が授業で触れた点の理解をお願いします。
さあ、「権利関係」は残すところ2回です。
「宅建業法」へ進む前に、できるだけ復習をして、知識を定着させておきましょう!

2019年05月23日
「宅建 実力養成講座」のご案内
本年度も、SBS学苑 パルシェ校にて「宅建 実力養成講座」を開講致します。
この講座は、(要点整理テキスト)を用いて行う、
宅建試験の「重要論点」「頻出事項」の短期集中型講座です。
もともとは、中・上級者向けに企画した講座ですが、初学者の方でもかまいません!
さあ、あなたも、今年の合格に向けて参加しませんか!
[開講日]
パルシェ校のみ :2019年7月17日(水)19:00~21:00 全12回
※ 最終回:10月6日(日)13:00~16:00 直前予想模擬試験
〈 無料ガイダンス 〉 6月26日(水) 19:00~20:00
http://www.sbsgakuen.com/Detail?gakuno=2&kikanno=192380
※詳しくは、学苑事務局(054-253-1221)までお問い合わせ下さい。

2019年05月20日
(第10回) 講義のポイント
いずれも頻度の高い項目ですので、テキストの理解と、
繰り返しの過去問演習を心がけましょう。
「根抵当権」
①意義・「極度額」と「元本確定」の理解
②附従性と随伴性がないことの理解
「時効」
①「取得時効」の意義と要件 ※事例を想起できるようにすること
②「消滅時効」の意義と要件 ※事例を想起できるようにすること
③「時効の中断」の意義、中断事由の理解
「相続」
①意義
②「法定相続」における「相続人」と「相続分」を覚えること
今回で、カリキュラムの3分の1が終了しました。
一番の難所である「民法」も、もうすぐ終わります。
ここを抜ければ、「宅建業法」という、
<配点は高いけれども、理解は難しくない>分野に進みますので、
皆さん、もう少しがんばりましょう!

2019年05月13日
(第9回) 講義のポイント
法定担保物権である「留置権」「先取特権」と、
本試験でも、実務でも重要な、「抵当権」です。
「留置権」「先取特権」
①意義、制度趣旨、効力
②授業で私が話した具体例をイメージできるようになること
「抵当権」
①意義・性質(とりわけ「物上代位性」)・債権と物権の世界における
各々の当事者の呼び名
②(あまりにも項目が多いので)授業で私が解説した部分と、
過去問のマーキングがある部分の理解
③P119(建物を保護するための制度)、
P122(第三取得者を保護するための制度)は、
一度、自分で図式化した上で納得しておくこと
何度も言うようですが、「抵当権」は必ずと言っていいほど
出題されますので、どこからどう問われても解答できるよう、
たくさんの過去問を解いておきましょう!

2019年05月07日
「住宅金融支援機構」関連ニュース
「フラット35」という住宅ローンの不正利用をめぐるニュースです。
https://news.yahoo.co.jp/pickup/6322639
ご自分で家を買う際に、長期・固定のローンを組んだりしない限り、
一般にはなじみの少ないものなので、
こうしたニュースを通じて、制度に触れておくことに意味があると思います。
ただ、すそ野を広げ過ぎないようにご注意下さい。

2019年05月02日
(第8回) 講義のポイント
第8回目(権利関係7)は、「連帯債務」「用益物権・相隣関係」
「担保物権一般・質権」の学習です。
「債権」の世界がひと段落し、いよいよ「物権」の本格的な学習に入りました。
将来の実務を見据えながら、楽しく学習していきましょう。
「連帯債務」
①意義、保証・連帯保証との違い
②「絶対的効力事由」の理解と、6項目の暗記
時間とのかねあいもあり、授業では、P90、91をつぶさに読みませんでしたが、
ご自分で一度は読んでおきましょう
「用益物権」
①意義、所有権との違い
②地上権の意義、(土地の)賃借権・借地権との関係性の理解
③地役権の意義
「相隣関係」 授業で読んだ部分の理解
「担保物権一般」
①担保物権の意義、「留置的効力」と「優先弁済的効力」の理解、
4種類の担保物権の分類
②担保物権の性質(附従性・随伴性・不可分性)⇒物上代位性は次回
「質権」
①意義、物上保証(人)の意義
②授業で話した具体例を想起できるようにしておくこと
さあ、新しい時代が始まりました。 皆さんは、 「令和」初年度の合格者になるべく、 GW後も、「今年、合格する!」という意識を持続していきましょう!