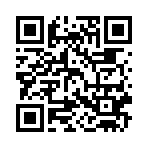2012年03月30日
「要点整理テキスト」のサブノート化
ガイダンスでもお話ししましたが、本試験に臨むに当たり、
我々は結局、重要なことがらを「覚えて」いかなければ、話になりません。
そして、「覚える」ためには、それにふさわしい環境と、然るべきツールが必要です。
(皆さんも学生時代、試験前に、何らかの暗記用ツールを作ったり、使ったことでしょう。)
現代の資格試験の学習では、以前あった、「大学ノートに重要事項を書き込み、色分けしていく」
ようなサブノート作りは、主流の学習法とは言えません。
受験生も、仕事やプライベートで何かと忙しいため、ツールを作るのにも、
スピード化が求められるのです。
そこで、サブノート作りのより効率的な方法として、
基本書や大学ノートではなく、「要点整理テキスト」を色分けし、これをサブノート化しましょう!
ちなみ私は学生時代から、次のやり方を実践してきています。
もしよろしければ、参考にして下さい。
[主に色分けで使うもの]
・硬筆(硬質)の色鉛筆⇒芯が硬いので折れにくいですし、細くきれいな線が引けます。
・定規
[項目別の色分けの仕方]
法律用語=青色(青ペン)/用語の意味=赤色/制度趣旨・理由づけ=緑色
重要なことがら※=水色/判例=ピンク色/具体例=紫色
※「どこが重要なのかわからない」段階では、まだ線を引いてはいけません。
テキストを読み、過去問を解いて、ご自分で重要なことがらを把握できた時点で色分けして下さい。
このように色分けをしますと、テキストを開いたときに、どこに何が書いてあるか、
一目瞭然です。「急がば回れ」サブノート作りには、当然時間を費やしますが、
このツールを使った学習効果は、非常に高いものになります。
もし、やり方がわからなければ、授業の際に私に質問して下さい。
私の、色分けしたテキストをお見せします

我々は結局、重要なことがらを「覚えて」いかなければ、話になりません。
そして、「覚える」ためには、それにふさわしい環境と、然るべきツールが必要です。
(皆さんも学生時代、試験前に、何らかの暗記用ツールを作ったり、使ったことでしょう。)
現代の資格試験の学習では、以前あった、「大学ノートに重要事項を書き込み、色分けしていく」
ようなサブノート作りは、主流の学習法とは言えません。
受験生も、仕事やプライベートで何かと忙しいため、ツールを作るのにも、
スピード化が求められるのです。
そこで、サブノート作りのより効率的な方法として、
基本書や大学ノートではなく、「要点整理テキスト」を色分けし、これをサブノート化しましょう!
ちなみ私は学生時代から、次のやり方を実践してきています。
もしよろしければ、参考にして下さい。
[主に色分けで使うもの]
・硬筆(硬質)の色鉛筆⇒芯が硬いので折れにくいですし、細くきれいな線が引けます。
・定規
[項目別の色分けの仕方]
法律用語=青色(青ペン)/用語の意味=赤色/制度趣旨・理由づけ=緑色
重要なことがら※=水色/判例=ピンク色/具体例=紫色
※「どこが重要なのかわからない」段階では、まだ線を引いてはいけません。
テキストを読み、過去問を解いて、ご自分で重要なことがらを把握できた時点で色分けして下さい。
このように色分けをしますと、テキストを開いたときに、どこに何が書いてあるか、
一目瞭然です。「急がば回れ」サブノート作りには、当然時間を費やしますが、
このツールを使った学習効果は、非常に高いものになります。
もし、やり方がわからなければ、授業の際に私に質問して下さい。
私の、色分けしたテキストをお見せします


2012年03月13日
「合格体験記」を大いに参考にしよう!
皆さんにお配りした「合格体験記」は、まさにプライスレスな価値を持っています。
学習方法は、まさに十人十色ですが、合格者に共通しているのは、
悩み、もがき、苦しみ、そしてたゆまぬ努力を続けた結果、栄光を手にしている点です。
誰一人として、楽をして合格した人はいません。
私も、昔は受験生だったわけですので、私の言うことも聞いていただきたいのですが、
それよりも、直近で合格された、皆さんと同じ受講生の方々の、ものの考え方・学習方法は
非常に参考になると思います。
ウェブ上にもたくさんの体験記が見れますが、
通学講座で同じカリキュラムで、同じテキストを使用していないと意味がないので
あまりお勧めできません。
開講間もないこの時期では、初学者の方は、
「体験記」の内容にピンとこないところもあると思いますので、
ぜひ、2度3度と読んで、合格者のことばから、たくさんのものを盗んで下さい。
今年、合格して、次の「合格体験記」を書くのは、あなたです。
その”合格のイメージ”をもって、日々過ごしましょう。

2012年03月12日
3.11 への想い
昨年度のSBS学苑「宅建合格講座」も、本年度と同じ3月第1週に開講し、
いよいよ本格的に授業だという、第2回目の授業の直前、3月11日にあの大震災が発生しました。
震災時、私は自分の会社で仕事をしていました。
大きな揺れだったので、すぐにテレビのスイッチを入れ、情報収集を始めました。
最初は、報道も混乱し、被害の全容を把握できませんでしたが、
次第にその惨状が明らかになって行きました。
東京電力管内にある沼津校は、計画停電の影響を受け、通常の木(夜)の授業はできず、
何日かは日曜日の午前中に授業をせざるを得ませんでした
(その結果、「日曜日では出席できない」との理由で、受講をやめざるをえなかった方もいました)。
「静岡にいる我々に、何かできることはないか」との想いで、
受講生の皆さんに募金を呼びかけたところ、皆さん快く趣旨に賛同して下さり、
震災の翌週には、静岡新聞社へ義援金を寄託することができました。
そして我々は、被災された方々に心を寄せつつ、
一方で、この震災から感じた「勉強できる喜び」を胸に、10月の本試験を目指しました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
震災から7カ月ほど経った10月21~23日に、私は静岡法人会青年部会の視察で、
宮城県女川町、石巻市、福島県郡山市等を訪れました。
街は少しずつ、復興に向けて動き出してはいるものの、建物などが基礎からごっそり流されており、
どこからどう手をつけてよいかわからない、圧倒的な虚無感に支配されていました。
私は、その被災状況を目の当たりにして、しばらく、声を出すこともできませんでした。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
そして、震災から1年。
我々は、与えられた命に感謝し、自然を畏(おそ)れ敬い、自然と共生していかなければなりません。
不動産のうち、「土地」は自然にあるものです。
「宅地建物取引主任者」は、その、自然にあるものを取り扱うお仕事です。
このことを肝に銘じ、我々は、「勉強できる喜び」を胸に、前へ進んでまいりましょう。
そして、試験に合格し、「宅地建物取引主任者」のライセンスを手に、
東北の、ひいては日本の復興を推し進める役割を担って行こうではありませんか!

いよいよ本格的に授業だという、第2回目の授業の直前、3月11日にあの大震災が発生しました。
震災時、私は自分の会社で仕事をしていました。
大きな揺れだったので、すぐにテレビのスイッチを入れ、情報収集を始めました。
最初は、報道も混乱し、被害の全容を把握できませんでしたが、
次第にその惨状が明らかになって行きました。
東京電力管内にある沼津校は、計画停電の影響を受け、通常の木(夜)の授業はできず、
何日かは日曜日の午前中に授業をせざるを得ませんでした
(その結果、「日曜日では出席できない」との理由で、受講をやめざるをえなかった方もいました)。
「静岡にいる我々に、何かできることはないか」との想いで、
受講生の皆さんに募金を呼びかけたところ、皆さん快く趣旨に賛同して下さり、
震災の翌週には、静岡新聞社へ義援金を寄託することができました。
そして我々は、被災された方々に心を寄せつつ、
一方で、この震災から感じた「勉強できる喜び」を胸に、10月の本試験を目指しました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
震災から7カ月ほど経った10月21~23日に、私は静岡法人会青年部会の視察で、
宮城県女川町、石巻市、福島県郡山市等を訪れました。
街は少しずつ、復興に向けて動き出してはいるものの、建物などが基礎からごっそり流されており、
どこからどう手をつけてよいかわからない、圧倒的な虚無感に支配されていました。
私は、その被災状況を目の当たりにして、しばらく、声を出すこともできませんでした。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
そして、震災から1年。
我々は、与えられた命に感謝し、自然を畏(おそ)れ敬い、自然と共生していかなければなりません。
不動産のうち、「土地」は自然にあるものです。
「宅地建物取引主任者」は、その、自然にあるものを取り扱うお仕事です。
このことを肝に銘じ、我々は、「勉強できる喜び」を胸に、前へ進んでまいりましょう。
そして、試験に合格し、「宅地建物取引主任者」のライセンスを手に、
東北の、ひいては日本の復興を推し進める役割を担って行こうではありませんか!

2012年03月10日
「過去問到達度チェックシート」について
授業の中でもご説明しましたが、「過去問到達度チェックシート」を使って、
過去問演習を効果的に行ってまいりましょう。
あらためて「チェックシート」の効用を確認しますと、
①自分がそれまで何問解いたのか、それをいつ解いたのか等が記録できる。
②解いた問題数が増えていくことがやりがいになる。
③講師に進度を確認してもらうことでアドバイスを受けやすい。
等が挙げられます。
テキストを読んでいるだけでは、「知識」は脳に定着しません。
テキストを読んで、「知識」をチャージ(充電)したあとは、
自分がそれを理解しているかどうかを問題演習によって検証する必要があります。
このチェックシートの提出は、決して義務ではありませんが、
3月から本試験まで、継続的にお出しになることをお勧め致します

過去問演習を効果的に行ってまいりましょう。
あらためて「チェックシート」の効用を確認しますと、
①自分がそれまで何問解いたのか、それをいつ解いたのか等が記録できる。
②解いた問題数が増えていくことがやりがいになる。
③講師に進度を確認してもらうことでアドバイスを受けやすい。
等が挙げられます。
テキストを読んでいるだけでは、「知識」は脳に定着しません。
テキストを読んで、「知識」をチャージ(充電)したあとは、
自分がそれを理解しているかどうかを問題演習によって検証する必要があります。
このチェックシートの提出は、決して義務ではありませんが、
3月から本試験まで、継続的にお出しになることをお勧め致します


2012年03月08日
遠鉄校 第1回講義を終えて
昨日、SBS学苑 遠鉄校にて、「宅建合格講座」第1回目の講義を行いました。
遠鉄校の受講生の皆さん、お疲れさまでした。
遠鉄校は昨年できたばかりですので、事前ガイダンスを除く、
正式なものとしては初めての講義でした。
お教室は、遠鉄百貨店新館の8階にあるのですが、
エレベーター、受付、フロアー、トイレに至るまで、その素材感、照明の感じなどが、
まるで高級ホテルのような美しさです。
受講生の皆さんもお勉強に身が入るのではないでしょうか。
パルシェ校同様、とても意欲的な雰囲気を持った受講生の皆さんでしたので、
私も、毎週水曜日に浜松に行くのが楽しみになりました。
今年の合格に向けて、一緒に頑張ってまいりましょう!
さあ、今日は沼津校の開講です。
沼津校の皆さんは、毎年、非常に意欲的ですので、今日の出会いが楽しみです

遠鉄校の受講生の皆さん、お疲れさまでした。
遠鉄校は昨年できたばかりですので、事前ガイダンスを除く、
正式なものとしては初めての講義でした。
お教室は、遠鉄百貨店新館の8階にあるのですが、
エレベーター、受付、フロアー、トイレに至るまで、その素材感、照明の感じなどが、
まるで高級ホテルのような美しさです。
受講生の皆さんもお勉強に身が入るのではないでしょうか。
パルシェ校同様、とても意欲的な雰囲気を持った受講生の皆さんでしたので、
私も、毎週水曜日に浜松に行くのが楽しみになりました。
今年の合格に向けて、一緒に頑張ってまいりましょう!
さあ、今日は沼津校の開講です。
沼津校の皆さんは、毎年、非常に意欲的ですので、今日の出会いが楽しみです


2012年03月07日
パルシェ校 第1回講義を終えて
パルシェ校の皆さん、昨日はお疲れさまでした。
初回でしたので、私も緊張していましたが、皆さんも緊張されていたことでしょう。
皆さんからは、非常に”前向きな良いエナジー”を感じましたので、
私の経験からすると、今年のパルシェ校からはまた、多くの合格者が生まれると思います

一緒に頑張っていきましょう!
昨日お話しした課題(「合格目標」「頻度表」をテキストに貼る件、
伊藤 真氏のテキストを読んでおく件、読者登録の件 など)は、
すぐにクリアして下さいね

※ SBS学苑「宅建合格講座」の講義は、毎回録画されているため、
講座途中からの入学も可能です。
詳しくは、SBS学苑 各校にお問い合わせ下さい。

2012年03月06日
本日、開講!
いよいよ、本日、本年度の「宅建合格講座」が開講します。
10月の本試験まで、足掛け8か月、今年絶対合格するために、頑張りましょう!
毎年のことですが、どのような方が受講生としてお見えになるのか、私も緊張します。
12月5日(水)の合格発表を、お互いに笑顔で迎えられるように、
とことん やり抜きましょう!

10月の本試験まで、足掛け8か月、今年絶対合格するために、頑張りましょう!
毎年のことですが、どのような方が受講生としてお見えになるのか、私も緊張します。
12月5日(水)の合格発表を、お互いに笑顔で迎えられるように、
とことん やり抜きましょう!

2012年03月05日
「税法」と「その他の分野」の学習について
講座が始まって第1回目の「宅建概論」でも申し上げますが、
「税法」と「その他の分野」の学習については、次の取り扱いでお願い致します
(いずれも初学者の方に対してです。複数回受験した方にはあてはまりません)。
■「税法」
9月に1コマ(2時間)の授業がありますが、
それまで過去問を解く必要はありません。
ただ、読みもの的にテキストの該当箇所をななめ読みするのは構いません。
なぜなら、9月にならないと、正確な法改正情報にのっとった学習ができないため、
法改正前の古い過去問を解いても意味がないからです。
授業が終わったら、一気に学習しましょう。それで十分間に合います。
■「その他の分野」
(土地の性質)(建物の性質)(住宅金融支援機構法)(景品表示法)(統計)
の5問分と、(不動産鑑定評価基準)(地価公示法)を指します。
7月に1コマ(2時間)の授業がありますが、
5問免除の方は、後の2項目のみの、その以外の方は全7項目の、
テキスト読みと過去問演習を、ご自分で3月からコツコツとやり進めていって下さい。
これら項目については、「民法」のような、法解釈論的な学習は必要ないため、
少なくとも過去に出題された範囲内については、一人で学習を進めていけるからです。
従って、7月の授業が、皆さんにとっての復習になるようなかたちが望ましいです。
さあ、明日から開講です!はりきってまいりましょう!

「税法」と「その他の分野」の学習については、次の取り扱いでお願い致します
(いずれも初学者の方に対してです。複数回受験した方にはあてはまりません)。
■「税法」
9月に1コマ(2時間)の授業がありますが、
それまで過去問を解く必要はありません。
ただ、読みもの的にテキストの該当箇所をななめ読みするのは構いません。
なぜなら、9月にならないと、正確な法改正情報にのっとった学習ができないため、
法改正前の古い過去問を解いても意味がないからです。
授業が終わったら、一気に学習しましょう。それで十分間に合います。
■「その他の分野」
(土地の性質)(建物の性質)(住宅金融支援機構法)(景品表示法)(統計)
の5問分と、(不動産鑑定評価基準)(地価公示法)を指します。
7月に1コマ(2時間)の授業がありますが、
5問免除の方は、後の2項目のみの、その以外の方は全7項目の、
テキスト読みと過去問演習を、ご自分で3月からコツコツとやり進めていって下さい。
これら項目については、「民法」のような、法解釈論的な学習は必要ないため、
少なくとも過去に出題された範囲内については、一人で学習を進めていけるからです。
従って、7月の授業が、皆さんにとっての復習になるようなかたちが望ましいです。
さあ、明日から開講です!はりきってまいりましょう!

2012年03月04日
まず、森を見よ!
皆さんとは、初めに「民法」を学習します。
以前も書きましたが、私法の一般法である民法は、1044条もの条文からなる
ボリュームのある法典で、我々の生活にとって、とりわけ重要な法律です。
宅建試験の学習としての「民法」は、司法試験や、司法書士試験のそれと異なり、
学習内容に若干の偏りがあるのですが(宅建民法では、法人や占有権はほとんど取り扱わない)、
それでも多くのことがらを学んでいきます。
その際に気を付けなければならない視点が、 「まず、森を見よ!」 ということです。
要するに、初めから1本1本の木をつぶさに見ていくのではなく、
森、すなわち”全体構造”を把握し、脳内にそのスペースを確保した上で、
その中に1本1本の木を収めていく(=内容を理解していく)という学習の進め方のことです。
民法は、次の5つの編から成り立っています。
第1編 総則
第2編 物権
第3編 債権
第4編 親族
第5編 相続
そして、一般的に、2・3編を「財産法」、4・5編を「身分法」と呼び、
同じ民法典の中にありながら、両者は性格を異にしています。
ここからの詳細は、授業の中でお話ししますが、今後の法律学習では、
まず、この全体構造を把握するクセをつけていって下さい。

2012年03月01日
本試験まで、残り234日!
今年の本試験は、10月21日(日)に実施されます。
今日は、3月1日。本試験まで、234日あります。
これを”まだ”と、とらえるか、”もう”と、とらえるかは、あなたの心持ち次第ですが、
一日一日が過ぎ去っていくスピードはとても速いので、
「今やれることは、やっておく」という基本姿勢で、毎日を悔いなく過ごしていきましょう!
皆さんに、栄光が訪れますように・・・