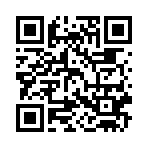2023年08月28日
「学習計画表」をフル活用しよう!
本試験まで、残り1ヶ月半です。
この残り期間を見渡せる「学習計画表」を作ることで、
学習を効率的に進めることができます。
早速、計画表作りに着手しましょう!
作り方の手順(例)は、次の通りです。
1. 9月と10月の2か月を見渡せるカレンダーを用意します。
書き込みをしますので、メモ書きできるスペースのあるものがベターです。
わざわざ買う必要はなく、インターネットで検索※して、プリントアウトすればいいでしょう。
※ 「2023年 9月 10月 カレンダー 画像」
2. カレンダーに、まず「本試験」、次に「答案練習」「直前予想模擬試験」を書き込みます。
→これが、皆さんのターゲットになります。
3. 「答案練習」「直前予想模擬試験」の前日は「調整日」とします。
→「調整日」は、あらかじめ科目を決めず、その都度 ご自分がウィークポイントにしている個所を
補強する日にあてます。
4. 残りの日は、主として主要3科目の総ざらえをしますので、
カレンダーに「パーフェクト宅建」(あるいは「要点整理」系)のページ数を記入し、
その日は、テキストの精読と過去問演習を行い、自分で納得のいく学習ができたら、
カレンダーの項目に×(バッテン)を書き込み、小目標をクリアしたこととします。
以上が概略ですが、本試験まで当初の計画通りにいくことはほとんどあり得ませんので、
途中 少なくとも2~3回は、計画を組みなおすことも想定して、着実に計画を実行して下さい。
ご不明な点は、授業の時などに私に聞いて下さい。
さあ、ゴールまであと少しです。気持ちを切らさずに、最後まで走り抜けましょう!
この残り期間を見渡せる「学習計画表」を作ることで、
学習を効率的に進めることができます。
早速、計画表作りに着手しましょう!
作り方の手順(例)は、次の通りです。
1. 9月と10月の2か月を見渡せるカレンダーを用意します。
書き込みをしますので、メモ書きできるスペースのあるものがベターです。
わざわざ買う必要はなく、インターネットで検索※して、プリントアウトすればいいでしょう。
※ 「2023年 9月 10月 カレンダー 画像」
2. カレンダーに、まず「本試験」、次に「答案練習」「直前予想模擬試験」を書き込みます。
→これが、皆さんのターゲットになります。
3. 「答案練習」「直前予想模擬試験」の前日は「調整日」とします。
→「調整日」は、あらかじめ科目を決めず、その都度 ご自分がウィークポイントにしている個所を
補強する日にあてます。
4. 残りの日は、主として主要3科目の総ざらえをしますので、
カレンダーに「パーフェクト宅建」(あるいは「要点整理」系)のページ数を記入し、
その日は、テキストの精読と過去問演習を行い、自分で納得のいく学習ができたら、
カレンダーの項目に×(バッテン)を書き込み、小目標をクリアしたこととします。
以上が概略ですが、本試験まで当初の計画通りにいくことはほとんどあり得ませんので、
途中 少なくとも2~3回は、計画を組みなおすことも想定して、着実に計画を実行して下さい。
ご不明な点は、授業の時などに私に聞いて下さい。
さあ、ゴールまであと少しです。気持ちを切らさずに、最後まで走り抜けましょう!
2023年08月18日
「宅建 答案練習&模擬試験 解答解説講座」 のご案内
本年度も、SBS学苑にて表記講座を開講致します
(答案練習2回と直前予想模擬試験1回の(計)3回)。
※ 3月からの「宅建士合格講座」の第28~30回がこれにあたりますので、
当該講座の受講生の方は、別途申し込み不要です。
10月の本試験に向けて、ご自分の実力を確認できるチャンスです。
さあ、あなたもふるってご参加ください!
[開講日]
パルシェ校 ( 054-253-1221):9月26日(火)、10月3日(日)、9日(月祝)
054-253-1221):9月26日(火)、10月3日(日)、9日(月祝)
[受講料]11,880円 ほか
※詳しくは、学苑 事務局までお問い合わせ下さい。

2023年08月17日
「個数問題」「組合せ問題」への対処法
近年、とりわけ「宅建業法」で出題数が増えている
「個数問題」「組合せ問題」ですが、
受験生はこれらにどう対処すべきでしょうか?
一般的に、「個数問題」「組合せ問題」は、「単純正誤問題」と比べて、
知識の正確性と、スピーディーな問題処理能力を必要とします。
従って、日ごろの家庭学習から、
〇条文の一字一句をないがしろにせず、一度は正確に(条文を)読んでみる。
〇過去の本試験で問われた、正答へのキーとなるポイント
(例えば、問題文にある「数字」など)が何であるか、
そして自分が間違えた点を洗い出してみる
⇒自分でデータを取って、弱点の傾向を見つけ出す。
〇試しに、これまでよりも、問題文を読むスピードを少し上げてみて、
自分の限界点(=正答率を落とさずに、
すべての問題を読み進めていけるスピード)を見つけ出す。
これらを意識して、得点を1点でも2点でも上積みできるよう、
工夫してみましょう。
「宅建業法」を制する者は、「宅建試験」を制します。
これをやれる時期は今しかありません。
さあ、「合格」に向けて、引き続きがんばりましょう!

「個数問題」「組合せ問題」ですが、
受験生はこれらにどう対処すべきでしょうか?
一般的に、「個数問題」「組合せ問題」は、「単純正誤問題」と比べて、
知識の正確性と、スピーディーな問題処理能力を必要とします。
従って、日ごろの家庭学習から、
〇条文の一字一句をないがしろにせず、一度は正確に(条文を)読んでみる。
〇過去の本試験で問われた、正答へのキーとなるポイント
(例えば、問題文にある「数字」など)が何であるか、
そして自分が間違えた点を洗い出してみる
⇒自分でデータを取って、弱点の傾向を見つけ出す。
〇試しに、これまでよりも、問題文を読むスピードを少し上げてみて、
自分の限界点(=正答率を落とさずに、
すべての問題を読み進めていけるスピード)を見つけ出す。
これらを意識して、得点を1点でも2点でも上積みできるよう、
工夫してみましょう。
「宅建業法」を制する者は、「宅建試験」を制します。
これをやれる時期は今しかありません。
さあ、「合格」に向けて、引き続きがんばりましょう!