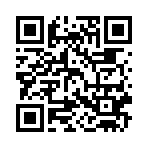2025年03月11日
「過去問演習」の方法
さて、「合格」に向けて注力しなければならない「過去問演習」ですが、
初学者の方は、そもそもやり方がわからないと思いますので、
次にその留意点を挙げます。

初学者の方は、そもそもやり方がわからないと思いますので、
次にその留意点を挙げます。
■ 「過去問」は、同じ問題を本試験までに少なくとも3~4回は解くものである。
但し、自分の中で完全に「この問題については理解できた」と実感したら、
もう解く必要はありません。代わりに他の同様の問題を解くべきです。
過去問はさかのぼれば、いくらでもあります。
■ 「過去問演習」の際には、ボールペンを使ってはいけない。
必ず鉛筆かシャープペンシルを使い、なるべく問題集そのものに
書き込みをしないようにしましょう。
なぜなら、先に申し上げた通り、過去問は同じ問題を複数回解くことが
通常なので、問題文上に痕跡を残してしまうと、次回以降、自らフラットに
学力をはかる際の妨げになるからです。
■ 世上、あまり言われていないことですが、
私は、 「過去問は古いものから解くべき」と考えます。
なぜなら、宅建試験の問題は、年々難易度が増しているからです。
従って、仮にあなたの目の前に、ある学習項目(例えば、民法の「代理」)の
令和5年、平成20年、平成15年の問題があるとしたら、
但し、自分の中で完全に「この問題については理解できた」と実感したら、
もう解く必要はありません。代わりに他の同様の問題を解くべきです。
過去問はさかのぼれば、いくらでもあります。
■ 「過去問演習」の際には、ボールペンを使ってはいけない。
必ず鉛筆かシャープペンシルを使い、なるべく問題集そのものに
書き込みをしないようにしましょう。
なぜなら、先に申し上げた通り、過去問は同じ問題を複数回解くことが
通常なので、問題文上に痕跡を残してしまうと、次回以降、自らフラットに
学力をはかる際の妨げになるからです。
■ 世上、あまり言われていないことですが、
私は、 「過去問は古いものから解くべき」と考えます。
なぜなら、宅建試験の問題は、年々難易度が増しているからです。
従って、仮にあなたの目の前に、ある学習項目(例えば、民法の「代理」)の
令和5年、平成20年、平成15年の問題があるとしたら、
平成15年⇒同20年⇒令和5年に並べ直して解くほうが、スムーズに理解でき、
脳に知識を納めやすいはずです。
■ 住宅新報出版の<分野別過去問題集>は解説も詳しく、すばらしい教材ですが、
掲載問題数が300問(⇒単純に考えて、本試験6ヶ年分)と少ないため、
学習に慣れてきたら、問題数が多く、解説が充実した
他の過去問題集を購入する必要があります。
購入するならば、予備校系(LEC・TAC・日建学院など)のものは、
解説も詳細で、バグも少ないのでおすすめです。
できれば、大きな書店で手に取って比較検討して下さい。
脳に知識を納めやすいはずです。
■ 住宅新報出版の<分野別過去問題集>は解説も詳しく、すばらしい教材ですが、
掲載問題数が300問(⇒単純に考えて、本試験6ヶ年分)と少ないため、
学習に慣れてきたら、問題数が多く、解説が充実した
他の過去問題集を購入する必要があります。
購入するならば、予備校系(LEC・TAC・日建学院など)のものは、
解説も詳細で、バグも少ないのでおすすめです。
できれば、大きな書店で手に取って比較検討して下さい。

2025年03月10日
必ず、「予習」をしよう!
現在、私たちが行っているのは、「法律」の学習です。
法律は、条文そのものが硬質ですから、その解説テキストもいきおい
硬い文章にならざるを得ません。
これを「初見で理解せよ」というほうが無理な話です。
そこで、授業に臨むにあたっては、
とりわけ初学者(=初めて「宅建」を学習する方)は、
テキストの下読み程度の「予習」をしてきたほうが、理解度が高まると思います。
「予習」の際には、
テキストの、(自分が理解しにくいところ)に、軽くしるしをつけておき、
私の講義がそこにさしかかったら、特に集中して聴く、
というやり方が効果的かと思います。
目安としては、2単元先くらいまで目を通しておけばいいでしょう。
授業は、1週間のうちのたった2時間しかありませんので、
そこからたくさんのものを家へ持ち帰り、
家庭学習でそれをふくらめたり、深掘りしたりするように心がけて、
日々 実力をつけていきましょう!

法律は、条文そのものが硬質ですから、その解説テキストもいきおい
硬い文章にならざるを得ません。
これを「初見で理解せよ」というほうが無理な話です。
そこで、授業に臨むにあたっては、
とりわけ初学者(=初めて「宅建」を学習する方)は、
テキストの下読み程度の「予習」をしてきたほうが、理解度が高まると思います。
「予習」の際には、
テキストの、(自分が理解しにくいところ)に、軽くしるしをつけておき、
私の講義がそこにさしかかったら、特に集中して聴く、
というやり方が効果的かと思います。
目安としては、2単元先くらいまで目を通しておけばいいでしょう。
授業は、1週間のうちのたった2時間しかありませんので、
そこからたくさんのものを家へ持ち帰り、
家庭学習でそれをふくらめたり、深掘りしたりするように心がけて、
日々 実力をつけていきましょう!

2025年03月05日
開講初日
昨日、めでたく

「令和7年度 宅地建物取引士試験」の合格を目指す、
「宅建士合格講座」が開講しました。
一昨日と打って変わって、
とても気温が低い日になりましたが、
ご出席の受講生の皆さんからは、
私の言葉の一言一句を聞き漏らすまい、との気迫を感じました。
私の使命は、そうした皆さんを合格に導くことです。
本試験までの足かけ8ヶ月間、
艱難辛苦を共に乗り越え、
一生の財産となる資格を手に入れましょう!
どうぞよろしくお願い申し上げます。

2025年03月04日
まず、森を見よ[民法の全体構造を把握しよう]
さて、皆さんとはまず、私法の一般法である民法から学習し始めますが、
民法は、1050条もの条文からなるボリュームのある法典で、
我々の生活にとって、とりわけ重要な法律です。
宅建試験の学習としての「民法」は、司法試験や司法書士試験のそれと異なり、
学習内容に若干の偏りがあるのですが
(宅建民法では、法人や占有権はほとんど取り扱わない)、
それでも多くのことがらを学んでいきます。
その際に気を付けなければならない視点が、

民法は、1050条もの条文からなるボリュームのある法典で、
我々の生活にとって、とりわけ重要な法律です。
宅建試験の学習としての「民法」は、司法試験や司法書士試験のそれと異なり、
学習内容に若干の偏りがあるのですが
(宅建民法では、法人や占有権はほとんど取り扱わない)、
それでも多くのことがらを学んでいきます。
その際に気を付けなければならない視点が、
「 まず、森を見よ! 」 ということです。
要するに、初めから1本1本の木をつぶさに見ていくのではなく、
森、すなわち”全体構造”を把握し、脳内にそのスペースを確保した上で、
その中に1本1本の木を収めていく(=内容を理解していく)という
学習の進め方のことです。
民法は、次の5つのかたまりから成り立っています。
第1編 総則
第2編 物権
第3編 債権
第4編 親族
第5編 相続
そして、一般的に、1・2・3編を「財産法」、4・5編を「身分法」と呼び、
同じ民法典の中にありながら、両者は性格を異にしています。
ここからの詳細は、授業の中でお話ししますが、今後の法律学習では、
まず、この全体構造を把握するクセをつけていって下さい。
要するに、初めから1本1本の木をつぶさに見ていくのではなく、
森、すなわち”全体構造”を把握し、脳内にそのスペースを確保した上で、
その中に1本1本の木を収めていく(=内容を理解していく)という
学習の進め方のことです。
民法は、次の5つのかたまりから成り立っています。
第1編 総則
第2編 物権
第3編 債権
第4編 親族
第5編 相続
そして、一般的に、1・2・3編を「財産法」、4・5編を「身分法」と呼び、
同じ民法典の中にありながら、両者は性格を異にしています。
ここからの詳細は、授業の中でお話ししますが、今後の法律学習では、
まず、この全体構造を把握するクセをつけていって下さい。