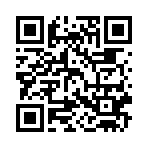2025年02月13日
「学習空間」の確保について
1週間のうちのわずか2時間(7日×24時間=168時間ですから)、
1週間のうちの、わずか84分の1に過ぎません。
一方で皆さんは、
睡眠・食事・用便・入浴等の、生きて行くために必要なことを行う時間を除いて、
仕事(通勤時間含む)・家事・子育て等を行わなければならないわけですから、
そこから貴重な”自習時間”を捻出していくことになります。
だとすると、その貴重な”自習時間”を、
最大限効果的に使うことを考えなければなりません。
それを実現するためには、
「モチベーションの維持」「やる気」「集中力」など、
主にメンタル面の要素が重要になりますが、
それとともに考えておかなければならないことは、
学習効果を最大限に高めることができる、<学習空間の確保>です。
『テキストを読み込む』⇒『過去問を解く』⇒『重要項目を覚える』
合格のために必要な、この各プロセスをどのような空間で行うか、
自宅の自分の部屋/自宅のリビング/車の中/会社の自席/
スクールの待合所・教室/カフェ/図書館 など、
どこが自分に合っているのか、
今からその戦略を考えておいたほうがよいでしょう。

2025年02月05日
「民法」学習にあたり、おススメしたい本
その「合格講座」第1回目の「宅建概論」でもお話ししますが、
皆さんとは最初に、民法を学習するということもあり、
事前にぜひ読んでおいていただきたいテキストがあります。
それは、伊藤 真(著) 「伊藤 真の民法入門」
伊藤 真(まこと)氏は、言わずと知れたLEC創成期の司法試験部門を
作り上げた方で、法律系国家資格指導の第一人者です。
現在は、護憲派弁護士としても活躍されています。
民法は、我々の日常生活に密接な関係のある、非常に重要な法律です。
法律上の「人」とは何かから始まり、
契約(売買や賃貸借)・債務不履行・連帯保証・
抵当権・時効・相続等、ビジネスでも有用な知識を学習します。
ただ、我々が講座で使うテキストが、
(当たり前ですが)受験対策として書かれたテキストのため、
ともすると、とっつきにくく、
本来ならおもしろく、ためになるはずの民法の良さが
伝わりにくい恐れがあります。
そこで、この「民法入門」を事前に読んでおけば、比較的スムーズに、
民法のおもしろさを理解していただけると思うのです。
「民法入門」は口語体で書かれているため、
200ページほどの分量ですが、一気に読めてしまいますよ。
民法改正に対応した最新版は「第8版」になります。
さあ、皆さん、今すぐこの本を手に入れましょう!

2025年01月10日
「再受講」のススメ
いよいよ、SBS学苑「宅建士合格講座」の開講が迫ってきました。
過去に私の講座をお受けいただいた方の中には、
「再受講をしようかどうか」迷っていらっしゃる方もおられると思います。
そのような方に、私はこうお伝えしたいです。
「今年、絶対に合格するために、もう一度、一緒にがんばりましょう!」
10月の本試験までは、長丁場です。
そこで、まず必要なのは、 「ペースメーカー」です。
今 お持ちのモチベーションを維持しつつ、本試験で最高の実力を発揮できるように、
週1回の講義を受けに来て下さい。
もし、毎週の通学がたいへんならば、YouTube 受講との併用も可能です。
そこで、いつものように私があなたを ”叱咤激励” します。
同じテキストを使いますので、そう変わった話はできませんが、
あなた自身の理解力が、これまでとは違っているはずです。
今年受かればいいのです。
「再受講は恥ずかしい」なんていうことは考えなくても結構です。
なぜなら、それはあなたの人生であって、
自分に正直に、わがままであるべきだからです。
受かれば、確実に人生が変わります。
再受講で<合格>された方も、数多くいらっしゃいます。
もう一度言います。 ご一緒にやりましょう! お待ちしております。
迷っている方は、私まで直接ご連絡下さい。
054-247-9495 または tko@press-a.com
[受講を決められた方は、恐れ入りますが、すぐにSBS学苑までご連絡下さい。]

2025年01月08日
「マンガ教材」を活用しよう!

2024年09月06日
「宅建業法」をメインに考えよう!
ガイダンス時をはじめとして、ことあるごとに申し上げておりますように、
「宅建業法」は、50点中20点の”大票田”ですから、
ここでなんとしても、20点近くを取り、トータル38点の目標に向けて、
安定的に得点のデザインをしていくべきです。
『自分は”権利関係”のほうが好きだ』とか、
『不動産の実務をやっていないから、なんとなく業法が好きになれない』とか、
言っている場合ではありません
(それでもなじめないなら、いま一度「マンガ~」でも読みましょう)。
ここからの意識としては、業法、業法、業法です。
そして、その上で、他科目の得点水準を落とさないような、
バランスのとれた学習が必要です。
「権利関係」で1点取るよりも、「宅建業法」で1点を取るための
投下時間・投下エネルギーのほうが、少なくて済みます。
従って、残された時間で「宅建業法」に より注力することで、
短期間で、飛躍的に得点が伸びるはずです。
何度も言いますが、カギは「宅建業法」です。
過去何度も出ている、重要項目を確実に覚え、
それに関する分野別の過去問を徹底して解きましょう。
まだまだこれからです。
あなたなら、まだまだやれます。
来年もまた、同じ勉強をしなくて済むように、
本試験まであとわずか、集中して、がんばってまいりましょう!

2024年09月04日
「覚える」モードに入ろう!
ここからは、これまで学習してきたことを「覚える」モードに入るべきです。
過去問演習を継続することはもちろんですが、
要点整理系テキストなどを活用して、効率よく、集中して、
重要項目を覚えていきましょう!
どの資格試験でも、結局、覚えて行かないことには話になりません。
暗記が得意、不得意にかかわらず、
『合格』の頂(いただき)に向けて、日々 努力して参りましょう!
日中はまだまだ暑いですが、朝夕の風は秋めいています。
あと ひと月、がんばればいいのです。
あなたなら、できます。
なぜなら、ここまで気持ちを切らさずにがんばってきたからです。
私はもちろん全力で、最後まで、サポートいたします。
さあ、ともにがんばってまいりましょう!

2024年09月02日
「50問 ワンセット」の問題演習のやり方について
本試験まで、残りひと月半ほどとなり、最終段階の調整方法として、
「50問ワンセット」の過去問あるいは模擬試験にトライしはじめている頃かと思います。
これから「50問 ワンセット」の問題演習をするについては、
ぜひ、次の各点に留意して下さい。
①できるだけ、本試験と同じような演習環境をつくること
(静寂性の確保、途中で飲み物も口にしない、もちろん携帯電話など見ない 他)
②できるだけ、2時間を目いっぱい使うこと
(見直しを含めて2時間という”尺”を、体になじませる)
③解き終わった後は、必ず「得点バランス分析表」に、得点をあてはめ、
自分の弱点がどこにあるのかを探ること
①と②を愚直に行うことで、③の正確なデータが手に入ります。
さあ、ターゲットが近づいてきました。
最後まで、決してあきらめず、今日やれることを着実にこなしていきましょう!

2024年07月04日
「学力のピーク」は、いつ頃に照準を合わせるべきか?
受験生としては、 「学力のピーク」、すなわち、
皆さんの頭の中に、本試験で吐き出すべき知識がパンパンに詰まっている状態を
いつの時点に持っていくべきかということについて、
それはズバリ、<本試験の10日~2週間前くらい>です。
試験当日に、初めてピークが訪れるようではすでに遅いのです。
なぜなら皆さんは、模擬試験において、
少なくとも一度は38点以上を得点し、自信をもって本試験に臨むべきだからです。
この10日から2週間(=14日)のピーク期間に、さらなる弱点補強や微調整、
体調管理などをして、万全の態勢で、本試験に臨みましょう。
ですから、これからは前倒し、前倒しで学習計画のスケジューリングをする意識で、
一日一日を悔いなく過ごして下さい。
その先に、一生の輝きを放つ、価値ある資格が待っています。

2024年04月15日
「コンメンタール」の利用について
法律を学ぶ者にとって、その主な学習題材は「条文」と「判例」です。
特に「条文」は、法律学習の根本であって、それは学者も、皆さん方 受験生も同じです。
さて、それほど重要な「条文」なのですが、とりわけ現行民法のベースは、
今から128年前の1896(明治29)年に制定されたものということもあり、
言い回し自体が難解で、解釈に骨が折れるものであることは確かです。
そこで、皆さんの学習の助けになる、あるウェブページをご紹介します。
それは「コンメンタール 民法」というものです。
「コンメンタール」とは、ドイツ語で、「逐条解説(書)」という意味です。
私が学生の頃は、インターネットが普及していなかったため、
とても高価な、書籍としての「コンメンタール」を購入しなければなりませんでしたが、
今はとても便利になりました。
もし、民法の「条文」の解釈でわからないことがあったら、こちらのページをご覧下さい。
ただ、「コンメンタール」は、”深い森” ですので、
戻って来れないほど深入りするのは逆効果ですから、
適度な距離感でお使いになることをおすすめします。

2024年04月09日
すぐに「調べる」クセをつけよう!