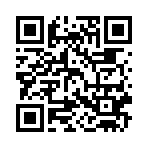2022年01月13日
「本格的な学習」に入る前に考えておきたいこと
先日、ネット記事で、

「これは!」と腑に落ちるものに出会いました。
論旨は、
知識の吸収度合いの差は、
もともと「勉強のできる人」と「できない人」の違いではなく、
知識を吸収する前段階の、”受け入れ態勢”の違いだ、
というものです。
以下に、その記事(実際はTwitter上のtweet)を引用します。
■篠原 信
(プロフィールは、こちらをご参照下さい
※下線は、このtweetのポイントと判断し、私が引きました。
「勉強できる子」は一度説明しただけで理解し、覚えてしまう。
「勉強の苦手な子」は一度説明しただけでは理解できず、
覚えることもできない。
この現象をもって「頭が悪い」と決めつけてしまう「勉強のできる人」は多い。
しかし私は見解が異なる。
観察していると「勉強のできる子」は、その言葉を聞く前にすでに知識の
ネットワークが準備されている。
電流の話を聞く前に、モーターや電球の仕組みだとかに興味を持ち、
すでにある体験ネットワーク、知識ネットワークの結節点の一つに
その名称をあてはめるだけ。だからすんなり覚えてしまう。
ところが「勉強が苦手な子」は、体験ネットワークがすっぽりと抜けて
しまっていることが多い。
花をマジマジ見たことがないし、電気のオモチャを分解したりしたことが
ない。
見たことも聞いたこともないことを突然聞かされても面食らうだけだし、
何度説明されても体験と結びつかず、理解できない。
私は、知識とは、知の織物「知織」だと考えている。
他の知識と断絶した知識はない。
たとえば「鉄」を理解するには、真夏の太陽に照らされた鉄は
火傷するほど熱いと言った体験や、逆に冬には凍てつくほど
冷たかったり、電気が通ったり、フライパンを熱して湯気が出たり、
磁石がくっついたり。
濡れるとサビたり。包丁のような刃物になったり。
そういった諸々の周辺的事実の結節点として、私たちは「鉄」を
初めて理解する。
知識とは知のネットワークを形成することであり、ことばを覚えるとは
結節点に名前をつけることであり、理解するとは、その結節点が
何とつながっているかを知ること。
「勉強の苦手な子」が、説明を一度されただけでは理解できなかったり、
場合によっては何度説明されても理解できないのは、その言葉を
受けとめるべき体験ネットワーク、知識ネットワークが欠如してるから。
何も受けてのないところに投げても落ちるだけ。
大切なのは、受けるネットワーク構築。
(中略)
だから、大切なことは教えるよりも体験させること。
不思議な思いに浸ること。
不思議に思えば興味関心が湧き、観察し、その仕組みを知ろうとする。
体験し尽くし、体験ネットワークができあがった時にそれぞれの
結節点の名前を聞くと、一度で覚えてしまう。
「ああ、あれはそんな名前だったのか!」
(後略)
■この篠原氏のtweet から、
我々は何を学び、いかに行動すべきかは、次回のブログで考えます。

本試験に”再挑戦”される方へ
わからないことは、すぐに調べよう!
「過去問到達度 チェックシート」の効用
[保存版] 民法と宅建業法の関連事項
「問題集」の特性・使用時期・活用法
「税法」「その他の分野」の学習について
わからないことは、すぐに調べよう!
「過去問到達度 チェックシート」の効用
[保存版] 民法と宅建業法の関連事項
「問題集」の特性・使用時期・活用法
「税法」「その他の分野」の学習について
Posted by 久保 剛(くぼ たけし) at 09:59
│学習方法




![[保存版] 民法と宅建業法の関連事項 [保存版] 民法と宅建業法の関連事項](http://img01.eshizuoka.jp/usr/t/a/k/takkengokaku/z_0107_main-s.jpg)