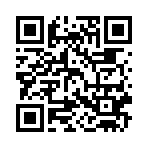2013年04月18日
[補講]委任契約と代理の差異
「権利関係 6」の講義の中で、委任契約を扱います。
委任契約とは、他人に契約などの法律行為をしてもらうことを委託する契約(民法643条)です。
委託する人を「委任者」、委託される人を「受任者」と言います。
ところで、このように、他人に法律行為を代わってやってもらうものとして、
皆さんとは既に「任意代理」を学習済みですね。
そこで、
「委任」と「代理」はどう違い、両者はどのような関係にあるのかを整理してみましょう。
まず、「代理」はA・B・Cの三者間の関係を規律するものです(テキストP20図 参照)。
つまり、代理人Bが本人Aのためにすることを示して、代理権の範囲内で、
相手方Cとの間で代理行為をなし、その法律効果が直接AC間に及びます。
これに対し、「委任」は、AB間の関係だけを規律するものであり、
受任者Bが委任者Aのために法律行為をする義務を、Aに対して負うというだけです。
受任者の相手方が委任者Aとどのような関係になるのかということは、
委任契約の射程範囲内には当然には入っていないのです。
従って、 「委任」と「代理」は異なるものであり、受任者が必ずしも代理人になるわけではなく
(受任者が代理人になるには、委任契約とは別に、代理権授与が必要であるというのが多数説)、
また、事務処理も必ずしも委任者の名を示してするわけではありません。
しかし、両者が極めて深い関係にあるのは事実であり、法律行為を委任する場合には、
事務処理の便宜上、代理権を授与するのが一般的です。
従って、委任者が代理でいう「本人」、受任者が「代理人」になることが実務上は多いと言えます。
以上ですが、本試験対策上は、その出題が「代理」の知識を問うているのか、
「委任契約」の知識を問うているのかは、一見してわかりますので、
それほど神経を使う必要はないと言えましょう。