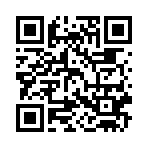2022年01月18日
誰も教えてくれなかった、究極の学習法
表題は、正確には、


「(あまたある学習法の中で、)誰も教えてくれなかった、
究極の学習法(のひとつ)」です。
名付けて、
「過去12年間<出題項目>把握 ローラー大作戦」です。
作戦内容を簡単に説明しますと、
過去12年間に出題された項目を、
テキストの中にマーキングして行き、
それによって、出題範囲と深度を把握し、学習効率を上げる
というものです。
作業には最初、時間と手間がかかりますが、
「急がば回れ」で、次のような絶大な効果をもたらします。
1.学習すべき出題範囲と、その深度を把握できる。
2. (1. により)「どこまで勉強すればいいのだろう」という
不安や、それによるストレスがなくなる。
3.何度も出題されている<頻出事項>を把握できる。
[用意するもの]
■2022年版 パーフェクト宅建士(基本書)
←3月からの講座で使用するテキストです。
■2022年版 パーフェクト宅建士(過去問12年間)
■鉛筆
[作業の手順]
(1)まず、(過去問12年間)の、令和3年度10月試験
の「正解と解説」を開く(P3)。
(2)問題1 の解説を読むと、肢1の解答に必要な知識は、
留置権に関する判決文による、
「敷金返還請求権に基づいて、賃借建物を留置できない」
という事項であることが分かる。
(3)これが(基本書)のどこに書いてあるかを探す。
留置権は担保物権であるから、P70から見ていくと、
P72の上から3行目の③に、その事項が書かれているので、
③の左側の空欄に、鉛筆でレ点を入れる⇒
もちろん、(過去問12年間)のほうにもレ点を入れておく。
以下、同様の作業を、問題14まで終えたら、
次は、令和2年度12月試験:問題1~14、
令和2年度10月試験:問題1~14、
令和元年度試験:問題1~14 というように、
まずは12年間の「権利関係」をすべて終わらせてしまう
(なぜなら、講座はまず「権利関係」から行うため、
皆さんが当面学習するのは「権利関係」だからである。
「権利関係」の次は、「宅建業法」⇒「その他の分野(「統計」除く)」
⇒「法令上の制限」と、講座カリキュラムの順に行っていく。
「税法」はやらなくてよい)。
[作業上の注意点]
本試験問題の中には、当該(基本書)に記述がないものも
存在する。(例)令和3年度10月試験:問題10肢4 など
このような場合には、(過去問12年間)のほうに、×印を書く。
また、(基本書)の該当箇所を探しても見つからない場合には、
いったん(過去問12年間)のほうに、△印を入れておき、
後日 再度探してみると見つかることがある
(もちろん、結局(基本書)に記述がない場合もある)。
以上の作業を、講座が始まる前に終わらせておくのが理想だが、
相応の時間と集中力が必要となるので、
自分の学習進度に合わせて、果実をもらたすと思える
タイミングで行えばよい。
さあ、今年必ず<合格>するために、
楽しみながら、この作戦を遂行しよう!