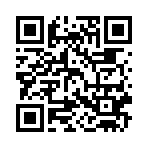2017年05月21日
「(土地の)賃借権の時効取得」について
今週の講義で、「時効」をやりました。
重要度からして、詳しく説明しませんでしたが、お二人の受講生から
『不動産賃借権を時効取得できる(判例:テキストP129、8行目)
ということがイメージできません』 というご質問を受けましたので、
当該事例につき解説したいと思います。
■(土地の)賃借権の時効取得が認められた事例
[最判昭和62年6月5日:判例時報1260号]
(事実)
賃借人(被告:Y)は、昭和25年5月に平野善徳(甲)から
建物を購入し、所有権移転登記を受けた。
土地は1600円/年の約束で賃借し、甲に支払っていたが、
昭和55年に磯野吉太郎(原告:X)から、
「土地所有者は自分であるから、建物を収去して、
土地を明け渡してもらいたい」旨の請求をされた。
登記簿上の土地所有者はXであり、結果的にYは、
所有者でない甲から借地していたわけであるが、
YはXからの土地明渡し請求に対し、
「すでに賃借権を時効取得しており、明け渡す義務はない」と争った。
これにつき、一審二審とも、Yの主張を認め、
最高裁もまたYの主張を認めることとなった。
(判決要旨)
他人(X)の土地の継続的な用益(この場合、賃借)という
外形的事実が存在し、かつ、その用益が賃借の意思に基づく
ものであることが客観的に表現されているときには、
民法163条により、土地の賃借権を時効取得するものと解すべきことは、
当裁判所の判例(※)とするところであり、他人(X)の土地の所有者と
称する者(甲)の間で締結された賃貸借契約に基づいて、
賃借人(Y)が平穏公然に土地の継続的な用益をし、かつ、
賃料の支払いを継続しているときは、前記の要件を満たすものとして、
賃借人(Y)は、民法163条所定の時効期間の経過により、
土地の所有者(X)に対する関係において右土地の賃借権を
時効取得するに至るとするのが相当である。
※最判昭和43年10月8日があります。
~以上です。
Yは、賃借権の準占有を始めた際、土地の所有者をちゃんと
確認していなかったようですから、善意有過失であり、
時効取得のためには、20年の期間を必要とします。
条文上で時効取得できるとされている権利は、所有権をはじめ
用益物権などの物権なのですから、この判例は、
いわゆる「債権の物権化傾向」のひとつの発露とも言えるでしょう。
実はこの事例は、複数の相続が絡んでおり、
Xと甲との関係も、もう少し複雑なのですが、上記の限りで
ご理解いただけるかと思います
(興味のある方は、ご自分で調べてみるのも良いですが、
深入りすることはあまりお勧めしません)。

重要度からして、詳しく説明しませんでしたが、お二人の受講生から
『不動産賃借権を時効取得できる(判例:テキストP129、8行目)
ということがイメージできません』 というご質問を受けましたので、
当該事例につき解説したいと思います。
■(土地の)賃借権の時効取得が認められた事例
[最判昭和62年6月5日:判例時報1260号]
(事実)
賃借人(被告:Y)は、昭和25年5月に平野善徳(甲)から
建物を購入し、所有権移転登記を受けた。
土地は1600円/年の約束で賃借し、甲に支払っていたが、
昭和55年に磯野吉太郎(原告:X)から、
「土地所有者は自分であるから、建物を収去して、
土地を明け渡してもらいたい」旨の請求をされた。
登記簿上の土地所有者はXであり、結果的にYは、
所有者でない甲から借地していたわけであるが、
YはXからの土地明渡し請求に対し、
「すでに賃借権を時効取得しており、明け渡す義務はない」と争った。
これにつき、一審二審とも、Yの主張を認め、
最高裁もまたYの主張を認めることとなった。
(判決要旨)
他人(X)の土地の継続的な用益(この場合、賃借)という
外形的事実が存在し、かつ、その用益が賃借の意思に基づく
ものであることが客観的に表現されているときには、
民法163条により、土地の賃借権を時効取得するものと解すべきことは、
当裁判所の判例(※)とするところであり、他人(X)の土地の所有者と
称する者(甲)の間で締結された賃貸借契約に基づいて、
賃借人(Y)が平穏公然に土地の継続的な用益をし、かつ、
賃料の支払いを継続しているときは、前記の要件を満たすものとして、
賃借人(Y)は、民法163条所定の時効期間の経過により、
土地の所有者(X)に対する関係において右土地の賃借権を
時効取得するに至るとするのが相当である。
※最判昭和43年10月8日があります。
~以上です。
Yは、賃借権の準占有を始めた際、土地の所有者をちゃんと
確認していなかったようですから、善意有過失であり、
時効取得のためには、20年の期間を必要とします。
条文上で時効取得できるとされている権利は、所有権をはじめ
用益物権などの物権なのですから、この判例は、
いわゆる「債権の物権化傾向」のひとつの発露とも言えるでしょう。
実はこの事例は、複数の相続が絡んでおり、
Xと甲との関係も、もう少し複雑なのですが、上記の限りで
ご理解いただけるかと思います
(興味のある方は、ご自分で調べてみるのも良いですが、
深入りすることはあまりお勧めしません)。