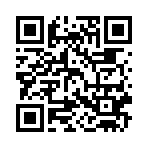2024年03月11日
「過去問演習」のしかた
さて、「合格」に向けて注力しなければならない「過去問演習」ですが、
初学者の方は、そもそもやり方がわからないと思いますので、
次にその留意点を挙げます。

初学者の方は、そもそもやり方がわからないと思いますので、
次にその留意点を挙げます。
■ 「過去問」は、同じ問題を本試験までに少なくとも3~4回は解くものである。
但し、自分の中で完全に「この問題については理解できた」と実感したら、
もう解く必要はありません。代わりに他の同様の問題を解くべきです。
過去問はさかのぼれば、いくらでもあります。
■ 「過去問演習」の際には、ボールペンを使ってはいけない。
必ず鉛筆かシャープペンシルを使い、なるべく問題集そのものに
書き込みをしないようにしましょう。
なぜなら、先に申し上げた通り、過去問は同じ問題を複数回解くことが
通常なので、問題文上に痕跡を残してしまうと、次回以降、自らフラットに
学力をはかる際の妨げになるからです。
■ 世上、あまり言われていないことですが、
私は、 「過去問は古いものから解くべき」と考えます。
なぜなら、宅建試験の問題は、年々難易度が増しているからです。
従って、仮にあなたの目の前に、ある学習項目(例えば、民法の「代理」)の
令和5年、平成20年、平成15年の問題があるとしたら、
但し、自分の中で完全に「この問題については理解できた」と実感したら、
もう解く必要はありません。代わりに他の同様の問題を解くべきです。
過去問はさかのぼれば、いくらでもあります。
■ 「過去問演習」の際には、ボールペンを使ってはいけない。
必ず鉛筆かシャープペンシルを使い、なるべく問題集そのものに
書き込みをしないようにしましょう。
なぜなら、先に申し上げた通り、過去問は同じ問題を複数回解くことが
通常なので、問題文上に痕跡を残してしまうと、次回以降、自らフラットに
学力をはかる際の妨げになるからです。
■ 世上、あまり言われていないことですが、
私は、 「過去問は古いものから解くべき」と考えます。
なぜなら、宅建試験の問題は、年々難易度が増しているからです。
従って、仮にあなたの目の前に、ある学習項目(例えば、民法の「代理」)の
令和5年、平成20年、平成15年の問題があるとしたら、
平成15年⇒同20年⇒令和5年に並べ直して解くほうが、スムーズに理解でき、
脳に知識を納めやすいはずです。
■ 住宅新報出版の<分野別過去問題集>は解説も詳しく、すばらしい教材ですが、
掲載問題数が300問(⇒単純に考えて、本試験6ヶ年分)と少ないため、
学習に慣れてきたら、問題数が多く、解説が充実した
他の過去問題集を購入する必要があります。
購入するならば、予備校系(LEC・TAC・日建学院など)のものは、
解説も詳細で、バグも少ないのでおすすめです。
できれば、大きな書店で手に取って比較検討して下さい。
脳に知識を納めやすいはずです。
■ 住宅新報出版の<分野別過去問題集>は解説も詳しく、すばらしい教材ですが、
掲載問題数が300問(⇒単純に考えて、本試験6ヶ年分)と少ないため、
学習に慣れてきたら、問題数が多く、解説が充実した
他の過去問題集を購入する必要があります。
購入するならば、予備校系(LEC・TAC・日建学院など)のものは、
解説も詳細で、バグも少ないのでおすすめです。
できれば、大きな書店で手に取って比較検討して下さい。