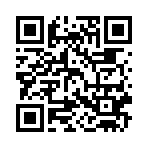2020年02月07日
合格体験記 9(中)
パルシェ校 N.K さん(静岡市 30歳代 女性)
[前回からの続き]
■各科目の学習方法(復習方法)
<権利関係>
権利関係(特に民法)は、とにかく慣れるのに時間がかかりました
(結局、ようやく馴染んだのは物権が終わる6月頃でした)。講義がどんどん
進んでしまう中で、常に先生の「まず森を見よ」の言葉を意識し、全体の理解を
見失ったまま進捗してしまわないよう、早めに復習に取り掛かりました。
また、解らない箇所(特にせっかく過去問を解いても、「解説」が未履修の単元を
含め説明していて、意味が全く理解できないことが多かったです)があれば、
その日のうちに先生にメールで質問させていただきました。
先生が即時に解説して下さり、お忙しい中、お電話で対応して下さることも何度も
ありました。おかげさまで、最終的には民法が得意科目になり、直前模試では
14問中13点を取ることができました。
具体的な復習方法は、①頻度表に合わせた見直し②自分の苦手単元の見直し
の2巡が必要でした。
①は、過去問の解き直しをしました。時期は、ゴールデンウィークで、講義がお休みに
なった期間、先生からいただいた頻度表中の5年以上/10年中に絞り込みました。
②は、テキストの読み直し・精読+もう一度 講義の聴き直しをしました。
通常の講義の進捗が終盤に差し掛かる上で、もう一度 原点回帰できたため、
単元と単元が結びつき、ここで初めて「木を見て、森を見られた」実感がありました。
時期は6月中旬~8月にかけて取り組みました。
<宅建業法>
内容の理解に苦慮する民法とは異なり、講義の中である程度身についた実感があった
こと、また、合格の得点源になる科目として違った訓練が必要だったことから、再度の
インプットは行わず、アウトプットに徹しました。講義の進捗と並行した毎週の復習に使う
過去問題集に、LECのものを1冊加え、翌週の講義までの間で、ある程度の状態まで
もって行けるようにしたつもりでした。
しかしながら 9月の答練では、13/20点しか取れず、たいへん焦りました。
もはや直前期にインプットにかけられる時間は限られ、テキストを頭から読み直す余裕は
ないため、最重要頻出ながら理解できていると思い込んでいた箇所(特に35条と37条、
免許と登録)に絞り込みをし、いわゆる”あんちょこ”を作りました。
ダイニングテーブルのマットに挟み込み、しょっちゅう見ることで、視覚から叩き込む
インプット方法をとりました。
<法令上の制限/税法/その他>
秋口の講義であるタイミング上、業法以上に直前期までに もう一度見直しをする余裕は
ありませんでした。それを覚悟した上で毎週の講義に臨み、1週間の復習の中で
落とし込みをおよそ完結できるようにしました。
「要点整理テキスト」を見直してみると、過去問の解説などから拾い出して、テキストに
自分で書き込んだメモ書きが一番多かった科目でした。
■直前期の勉強方法
「答案練習 Ⅰ」(9月24日)を控え、その1週間前からは本番に向けた訓練に集中することに
決めていました。市販の予想問題集を8冊購入し、毎日必ず1回分、時間を計って途中で
区切ることなく解きました。初めて解いた日は「これで全く得点できなかったらどうしよう…」
と本当に不安でしたが、答練当日までの1週間でもコンスタントに35点前後取れていました。
解き進める科目の順番や、時間配分、筆記用具も本番仕様に揃え、それなりに自信を持って
挑んだ「答練 Ⅰ」当日、本番さながらの緊張感に、想定外にも飲みこまれてしまい、
全く普段通りに解くことができませんでした。結果は28点、業法は13点。正直、ショックで
茫然としましたが、立ち止まる暇はない中で確信はありませんでしたが、このまま予想問題
1日1回分を続けることを主軸にし、宅建業法だけは過去問題集を40分間で解くことを
加えました。最終的に試験前々日までに30回以上、予想問題に取り組むことができ、
宅建業法も、最低17/20点まで水準を上げることができました。
加えて、予想問題集で間違えたところや知らなかった知識を「要点整理テキスト」に
落とし込んでいく作業を加えました。テキストを見直すと、書いてあるのに読み飛ばしていた
ことが多く、マーカー+付箋をしました。記載がなければ、手で書き込む時間さえも
惜しかったため、解説集を40%程度にコピーし、テキストの該当箇所にペタペタと貼りつけ
+付箋をしました(この付箋が、試験当日までの指標・宝になりました!)。 (続 く)

[前回からの続き]
■各科目の学習方法(復習方法)
<権利関係>
権利関係(特に民法)は、とにかく慣れるのに時間がかかりました
(結局、ようやく馴染んだのは物権が終わる6月頃でした)。講義がどんどん
進んでしまう中で、常に先生の「まず森を見よ」の言葉を意識し、全体の理解を
見失ったまま進捗してしまわないよう、早めに復習に取り掛かりました。
また、解らない箇所(特にせっかく過去問を解いても、「解説」が未履修の単元を
含め説明していて、意味が全く理解できないことが多かったです)があれば、
その日のうちに先生にメールで質問させていただきました。
先生が即時に解説して下さり、お忙しい中、お電話で対応して下さることも何度も
ありました。おかげさまで、最終的には民法が得意科目になり、直前模試では
14問中13点を取ることができました。
具体的な復習方法は、①頻度表に合わせた見直し②自分の苦手単元の見直し
の2巡が必要でした。
①は、過去問の解き直しをしました。時期は、ゴールデンウィークで、講義がお休みに
なった期間、先生からいただいた頻度表中の5年以上/10年中に絞り込みました。
②は、テキストの読み直し・精読+もう一度 講義の聴き直しをしました。
通常の講義の進捗が終盤に差し掛かる上で、もう一度 原点回帰できたため、
単元と単元が結びつき、ここで初めて「木を見て、森を見られた」実感がありました。
時期は6月中旬~8月にかけて取り組みました。
<宅建業法>
内容の理解に苦慮する民法とは異なり、講義の中である程度身についた実感があった
こと、また、合格の得点源になる科目として違った訓練が必要だったことから、再度の
インプットは行わず、アウトプットに徹しました。講義の進捗と並行した毎週の復習に使う
過去問題集に、LECのものを1冊加え、翌週の講義までの間で、ある程度の状態まで
もって行けるようにしたつもりでした。
しかしながら 9月の答練では、13/20点しか取れず、たいへん焦りました。
もはや直前期にインプットにかけられる時間は限られ、テキストを頭から読み直す余裕は
ないため、最重要頻出ながら理解できていると思い込んでいた箇所(特に35条と37条、
免許と登録)に絞り込みをし、いわゆる”あんちょこ”を作りました。
ダイニングテーブルのマットに挟み込み、しょっちゅう見ることで、視覚から叩き込む
インプット方法をとりました。
<法令上の制限/税法/その他>
秋口の講義であるタイミング上、業法以上に直前期までに もう一度見直しをする余裕は
ありませんでした。それを覚悟した上で毎週の講義に臨み、1週間の復習の中で
落とし込みをおよそ完結できるようにしました。
「要点整理テキスト」を見直してみると、過去問の解説などから拾い出して、テキストに
自分で書き込んだメモ書きが一番多かった科目でした。
■直前期の勉強方法
「答案練習 Ⅰ」(9月24日)を控え、その1週間前からは本番に向けた訓練に集中することに
決めていました。市販の予想問題集を8冊購入し、毎日必ず1回分、時間を計って途中で
区切ることなく解きました。初めて解いた日は「これで全く得点できなかったらどうしよう…」
と本当に不安でしたが、答練当日までの1週間でもコンスタントに35点前後取れていました。
解き進める科目の順番や、時間配分、筆記用具も本番仕様に揃え、それなりに自信を持って
挑んだ「答練 Ⅰ」当日、本番さながらの緊張感に、想定外にも飲みこまれてしまい、
全く普段通りに解くことができませんでした。結果は28点、業法は13点。正直、ショックで
茫然としましたが、立ち止まる暇はない中で確信はありませんでしたが、このまま予想問題
1日1回分を続けることを主軸にし、宅建業法だけは過去問題集を40分間で解くことを
加えました。最終的に試験前々日までに30回以上、予想問題に取り組むことができ、
宅建業法も、最低17/20点まで水準を上げることができました。
加えて、予想問題集で間違えたところや知らなかった知識を「要点整理テキスト」に
落とし込んでいく作業を加えました。テキストを見直すと、書いてあるのに読み飛ばしていた
ことが多く、マーカー+付箋をしました。記載がなければ、手で書き込む時間さえも
惜しかったため、解説集を40%程度にコピーし、テキストの該当箇所にペタペタと貼りつけ
+付箋をしました(この付箋が、試験当日までの指標・宝になりました!)。 (続 く)